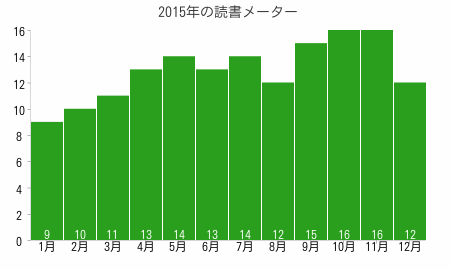
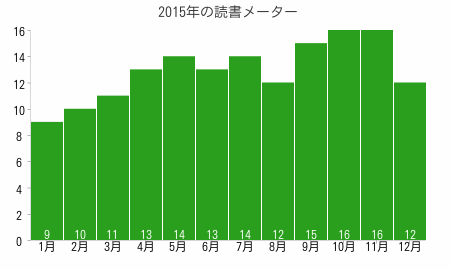
|
2015年の読書メーター 読んだ本の数:155冊 読んだページ数:45375ページ ナイス数:1043ナイス  ブラッドランド 下: ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (単行本)の感想 ブラッドランド 下: ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (単行本)の感想ソビエトとドイツがつるんでポーランドを侵略して大戦を始め、餓死、銃殺、移送、虐待に邁進する様は恐ろしい。殺害数を競わせて倫理的抵抗を薄れさせ、狂奔させた手口はスターリンもヒットラーも同じ。富農、知識人、少数民族、婦女子を暴行、殺戮する警察、軍隊に言葉を失う。戦後、各国で被害数を誇張し、被害者として正当化する態度は、そそのかされれば、激しい暴力に駆り立てられてしまう体質がそのままと。殺戮数を理解し、正当化を許さず、政権も許さない知識を持てと。つらい、良い本。但し、変換文のような翻訳には我慢。 読了日:12月31日 著者:ティモシースナイダー  日本、遥かなり エルトゥールルの「奇跡」と邦人救出の「迷走」の感想 日本、遥かなり エルトゥールルの「奇跡」と邦人救出の「迷走」の感想海外で交流を深めて誠実に賢明に仕事をしている日本人が、戦争、内戦、動乱、人質拘束に際し、機敏に、思慮深く協力し合い、トルコや現地の人々に助けられて生き延びた姿は胸に迫る。他国に救援してもらうしかない母国の情けなさを味わわされた人々だ。安全保証がないから救援機をださぬ日本。日本人の安全保証がないから救援機をだすトルコ。自国民が陸路脱出する中で救援機で日本人を救ったトルコ政府。その政府を責めぬトルコ国民。気高い国だ。日本の外務省も日本人も起こってほしくないことは起こらないことになっている体質だそうだ。 読了日:12月29日 著者:門田隆将  ブラッドランド 上: ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (単行本)の感想 ブラッドランド 上: ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (単行本)の感想スターリンが工業化推進、集団農場推進のため1932年ウクライナの食糧を国有として収奪して輸出してウクライナ人3百万人餓死させたと。その時、人肉が肉屋で売られている資料を佐藤優はみたことがあると読んだ。富農の抹殺のため収容所に1800万人入れ、数百万人を死亡させたと。この頃スターリンの妻は自殺。更に集団農場失敗を外国、政敵の陰謀とし、敵性民族、富農として62万人処刑。ヒトラーは占領したソ連領のユダヤ人を100万人銃殺、ソ連軍捕虜銃殺50万人、餓死・衰弱死260万人と。凄惨すぎる。 読了日:12月27日 著者:ティモシースナイダー  グアンタナモ収容所 地獄からの手記の感想 グアンタナモ収容所 地獄からの手記の感想21世紀に入っても差別的独善的野蛮行為が国家組織の行為として行われ、隠蔽され、虐げられている人々がいるとの告発だ。正義の復讐論に隠れて横暴な差別的蛮行を黙認する図式で、ニック・タースの「動くものはすべて殺せ」のベトナムでの米軍の体質と酷似。この地は1903年キューバからの永久租借地だが、カストロは租借料を1回のみ受け取り、以後認めず拒否と以前読んだ。ブッシュが設けてオバマは止めると言ったが止めない施設での話だ。解せない。 読了日:12月23日 著者:モハメドゥ・ウルドスラヒ  国道者の感想 国道者の感想2014年刊、ふしぎな国道もおもしろかったが、こちらも歴史、政治、行政に触れながら軽妙でおつな読み物。ふしぎな国道はマニアへの理解がはかられている感じだったが、今回は、国道の歴史的な営みの面白みを伝える感じで十分楽しめた。新潮45への長期連載の編集出版だが、最後まで人の営みを覗いたようで楽しめた。 読了日:12月21日 著者:佐藤健太郎  現場からオフィスまで、全社で展開する トヨタの自工程完結―――リーダーになる人の仕事の進め方の感想 現場からオフィスまで、全社で展開する トヨタの自工程完結―――リーダーになる人の仕事の進め方の感想日本の産業競争力の低下の要因に、意志決定の遅さがあるそうだ。スタッフの仕事の工程とは意思決定であって、意志決定する工程の品質、効率が「心がけ」で終わっていて、科学的な抜本的な意思決定の手順になっていないのが問題だそうだ。現場は非情に厳しい状況で戦ってきたが、ホワイトカラーは戦ったのか。生産現場の頑張りでスタッフ部門のたくさんの人が助けられてきたが、もう、まったなしの時代。迅速な正しい意思決定を効率的にできないと危ないぞと。トヨタは2007年から自工程完結の取り組みをホワイトカラーで始めたと。さすがだ。 読了日:12月15日 著者:佐々木眞一  月夜の記憶 (講談社文芸文庫)の感想 月夜の記憶 (講談社文芸文庫)の感想二つの精神的季節、私の中の戦中・戦後、靖国神社の三篇を読み、吉村昭の戦争に対しての考え、日本人の戦争に対する態度についての吉村昭の考えがよくわかった。手のひらを返したマスコミ、知的文化人は怯懦と。自身をふくめた人間へのぬぐいがたい不信感が胸に焼き付いていると。靖国神社は遺族が語り合い、慰めあう場と。政治に利用されては純粋さを失うと。 読了日:12月13日 著者:吉村昭  遠い日の戦争 (新潮文庫)の感想 遠い日の戦争 (新潮文庫)の感想非戦闘員に対するアメリカ軍の殺戮行為を理由に撃墜した爆撃機搭乗員を処刑した日本軍将兵の敗戦後の決意、逃亡生活、変節する日本人への憤り、諦観、時代への同化、命拾いへの執念、戦犯に対して批難から憐憫へ時をようせず変節する日本人への嫌悪、個人の命乞いを図り責任転嫁する高級将校達への憎悪など、アメリカによる私刑にさせされた日本人の心情が克明に描かれていた。戦争を理解するのに必要な真実の記録のひとつだ。 読了日:12月13日 著者:吉村昭  収容所(ラーゲリ)から来た遺書 (文春文庫)の感想 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 (文春文庫)の感想すばらしい本。人間の尊さ、穏やかで強い意志、同胞への親愛、希望を人に与える道義感、貫く人道主義、信義に応える人々。過酷な状況で凄みに溢れる生き方を静かに穏やかに明るく貫いた日本人に涙する。過酷使役、寒さ、飢え、密告、抑圧の中で、人を和ませる文化、創作がいかにかぐわしいものであったことか。悲惨な悲しい物語であるのに、未来が開かれるような清々しい人物伝だ。読めてよかった。 読了日:12月10日 著者:辺見じゅん  ベトナムの桜の感想 ベトナムの桜の感想山田長政が活躍した頃の時代を舞台にした兄弟、師弟、島民の誠実な物語で悲劇にも心和む味わいのある小説だった。毒殺されてしまうベトナムの日本人町の人徳あふれる顔役の名は仁左衛門。史実ではタイで戦功でとりたてられて活躍し、最後に毒殺された山田長政も通称仁左衛門。海洋民族として外洋で活躍する日本人であっても桜をめでる優しい民族と願っているような話だった。 読了日:12月8日 著者:平岩弓枝  日本とドイツ 歴史の罪と罰: 20世紀の戦争をどう克服すべきか (徳間文庫カレッジ)の感想 日本とドイツ 歴史の罪と罰: 20世紀の戦争をどう克服すべきか (徳間文庫カレッジ)の感想ドイツの良し悪しのある素顔を覗けた気になる本。ドイツの教育が荒れてるとは。10歳で進路選別の格差社会であるとは。ドイツがナチス犠牲者の人道的補償はしたが、戦時賠償はしていない国とは。親中親ロの反日論調の国だとは。記述内容が2009年なので、ますます今はどうなってるのか気になる本。でもやっぱり日本人は、明治からのドイツ盲信は醒めていないかも。明治海軍は脚気を英国臨床医学で回避したのに、陸軍軍医の森鴎外はドイツ医学に固執して脚気で大勢の死者をだした。輸入車数はドイツが一番だが、VWは性能詐欺を世界で犯してた。 読了日:12月6日 著者:川口マーン惠美  動くものはすべて殺せ――アメリカ兵はベトナムで何をしたかの感想 動くものはすべて殺せ――アメリカ兵はベトナムで何をしたかの感想ベトナム戦争でアメリカが犯した戦争犯罪が断罪されている。傍証資料は国立公文書館にあった軍自身による戦争犯罪捜査資料の供述書の数々だそうだ。おぞましい猟奇的凄惨な所業の数々が検証されており、アメリカの将校・指揮官が率先して部下に実行させていたことに驚愕する。殺害人数で戦功が評価され、非戦闘員婦女子老人赤ん坊までを大量虐殺し、敵勢力と偽装して点数を稼ぎ、叙勲、出世競争を繰り広げたそうだ。個人の逸脱行為ではなく、米軍の戦争犯罪だと。利己的で強欲な体質は米軍も同じようだ。やるせない。 読了日:12月4日 著者:ニック・タース  トヨタ式A3プロセスで仕事改革―A3用紙1枚で人を育て、組織を動かすの感想 トヨタ式A3プロセスで仕事改革―A3用紙1枚で人を育て、組織を動かすの感想事実の収集・理解、真因の分析、共通理解の醸成、対策の共同検討、対策実行の合意形成、実行計画の関係者調整、実行状況確認と問題修正、完成度の評価、改善サイクルの継続、こうしたことを、各層で、各員がオーナーシップ・主体的発意を発揮して学び続けてることを説く。これが人間性のある仕事と。トヨタ道場の心構えがなんたるかをアメリカ人に説かれた。得心できる内容。トヨタは強いはずだ。この思考法・進め方が、レポートサイズからエイスリーと米産業界で呼ばれているそうだ。 読了日:11月30日 著者:ジョンシュック  世界史を変えた薬 (講談社現代新書)の感想 世界史を変えた薬 (講談社現代新書)の感想薬の開発、発見の歴史的逸話が色々あり、分野違いの者にはとても面白い読み物だ。著者の評価の視点は健やかで前向きで気持ちがよかった。手術の歴史が古代に発見されているなど驚きだ。また、ノーベル賞級の第一人者でも泥々の功名心が渦巻いた逸話など欧米の貪欲な価値風土を見るようだ。利益独占の製薬会社に怒りの対抗を新薬で果たした日本人学者の話には気持ちが救われる。著者のような科学の語り部は敷居高のある者には有りがたい。お陰で心震える科学が覗けた。 読了日:11月28日 著者:佐藤健太郎  空飛ぶタイヤ(下) (講談社文庫)の感想 空飛ぶタイヤ(下) (講談社文庫)の感想ノンフィクションかのようで、事実に近い内容だ。被害者の慰謝料は5百万と少額だったようだ。犯罪を犯した会社のその後は小説とは少し違った現実だ。この話とは、全く逆の会社もあった。欠陥車だと証人喚問まで米国政治家にされて苛め抜かれても、NASAの検証にもゆるがずに品質を証明し、自社製品を磨き続ける日本の自動車会社は実存している。一方で、欠陥部品を世界に供給してしまったパーツメーカーもある。製造業は作り手の品格・能力が端的にでる仕事のようだ。 読了日:11月27日 著者:池井戸潤  空飛ぶタイヤ(上) (講談社文庫)の感想 空飛ぶタイヤ(上) (講談社文庫)の感想モチーフになった十年以上前に発覚して糾弾された企業犯罪をWIKIで確認してみた。経営者達や実行した品質管理者達は猶予付の実刑判決が確定していた。彼らはこの本のような人間達であったのだろうか。でなければあんな悪事や惨劇は起きなかろうが・・・ドイツ車による世界中での詐欺犯罪、日本の名門企業での粉飾決算などまだ起きている。欲に支配されて繰り返されてしまうのだろうか。 読了日:11月26日 著者:池井戸潤  福井モデル 未来は地方から始まるの感想 福井モデル 未来は地方から始まるの感想「北陸資本主義」清丸惠三郎では、励む気質が北陸三県の幸せの源泉で家族、地域、仕事、技術の好循環が紹介されていた。本書では循環がなぜできたのかがよくわかった。富山市の底つき体験、公平論克服、再生の論理と実践に頭がさがった。鯖江の寛容、進取、協働精神には感服次第。福井の人を育てる民度の高さ、勤勉さが、環境の激変にも地域を生き返らせ続けているのがよくわかった。確かに未来の始まる予感がしてきて嬉しくなれた。考える力の教育が肝要と。 読了日:11月25日 著者:藤吉雅春  空白の戦記 (新潮文庫 よ 5-9)の感想 空白の戦記 (新潮文庫 よ 5-9)の感想「太陽をみたい」は、沖縄の伊江島での守備隊と一緒に戦った島民、女子斬込隊の惨劇。日本の将兵は爆雷を背に戦車に身を投じたと。島民も集団自決を望み、どうせ死ぬなら太陽をみたいと壕を出る女子達。生き残った者の戦後の飢餓生活。「敵前逃亡」は、捕まり、逃亡し、前線復帰をはかるも、日本軍士官は、死なずに捕虜になったと断じ敵前逃亡として斬首処刑する。戦時の壊滅した精神の支配がむごい。「最後の特攻機」は司令長官による8月15日午後の特攻の記録。 読了日:11月23日 著者:吉村昭  脱出 (新潮文庫)の感想 脱出 (新潮文庫)の感想「他人の城」は、沖縄から鹿児島への疎開命令に服した人々を乗せた三隻と護衛駆逐艦三隻の船団中、雷撃沈没した対馬丸で生存した旧制中学三年の少年が、生存への死闘と疎開先での差別から、日本の県であるとの錯覚、本土と沖縄の無縁を知る。帰還すると荒れ果てた故郷で米軍支配下で生きる冷めた覚悟をする。日本が忘れてはならない歴史。「脱出」は樺太から北海道に脱出する現実が生活と生死の冷え冷えとした現実として日本の歴史を突きつける。「珊瑚礁」はサイパンでの戦火に炙られた住民の惨劇だ。 読了日:11月22日 著者:吉村昭  殉国―陸軍二等兵比嘉真一 (文春文庫)の感想 殉国―陸軍二等兵比嘉真一 (文春文庫)の感想沖縄戦に動員された15歳の旧制中学3年生が生き残った戦場の記録文学で、凄惨、無残、残忍な体験が綴られていた。兵も老人も婦女子も地上に動くものを一人残らず殺戮しようかとするかのようなアメリカ軍による爆殺・銃撃殺・火焔焼殺。自決か玉砕かと思い詰める住民。繰り広げられた自決、投身、子の封殺、狂乱、膿、腐臭、遺体散乱、薬殺・・・日本本土進攻時期を延期させるために長期間にわたって抵抗せんとしたとは。言葉を失う。確か「珊瑚礁」でもサイパンの民間人の惨劇が記されていた。 読了日:11月21日 著者:吉村昭  生きて帰ってきた男――ある日本兵の戦争と戦後 (岩波新書)の感想 生きて帰ってきた男――ある日本兵の戦争と戦後 (岩波新書)の感想高学歴ではない兵士にみる民衆史、敗戦史、復興史で日本人の実像史だ。学歴による階級社会であった戦前の日本の現実もよくわかる。日本国民の大多数の現実を正しく見られた気がする。戦後も軍人恩給で優遇される旧支配階級。かたや「国民のひとしく受忍しなければならなかった戦争被害」と整理して補償を切り捨てる国と司法。戦後のやるせない未始末史を突きつけられた。 読了日:11月18日 著者:小熊英二  雪の墓標―タコ部屋に潜入した脱走兵の告白 (1979年)の感想 雪の墓標―タコ部屋に潜入した脱走兵の告白 (1979年)の感想吉村昭が1971年に発表した逃亡の主人公の1年9か月間に亘る逃亡中、タコ部屋潜伏先での行いを戦後に贖罪する心震えるノンフィクションだ。1978年、遺族を捜し出し、北海道の民衆史研究者や市民、僧侶とともに遺骨発掘、供養を成し遂げる。悲しみと救われる思いが半ばする真実だ。1980年、1986年に吉村昭は同主人公の贖罪の姿を描いたが、本書は戦前日本の底辺の史実を明らかにしており、そのあまりに凄惨で狡猾な現実には言葉を失う。 読了日:11月17日 著者:小池喜孝,賀沢昇  アイルトン・セナ 確信犯の感想 アイルトン・セナ 確信犯の感想21年前、事故現場から空撮中継し、ヘルメットが力なく揺れたのを見たような気がする。ヒーローの事故死は衝撃だった。89年のシケインに入らず同チーム二台が張り合って直進して停止したシーンにはチームメイトでも譲らぬ競争心に息をのんだ。90年のスタート直後の第一コーナーでの衝突リタイアに拍子抜けした記憶もあったが、実は、本書の著者に予告していた冷酷な復讐であったとは驚いた。情報操作のない率直な時代との著者評にも得心。 読了日:11月14日 著者:LeoTurrini  黒澤 明 樹海の迷宮: 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971-1975の感想 黒澤 明 樹海の迷宮: 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971-1975の感想40年前のソビエト共産党時代の黒澤明の映画撮影の日誌と元の脚本とその変更点をまとめた大作。脚本の決定稿は特に感動的な物語。映画は91シーンからなっていたそうだが、もとの脚本は101シーンあり、フィルム不良やソ連からの短縮化要請で削除されたシーンや、変更されたシーンももとを読めて、尚更、素晴らしい話だった。今回が初出と。撮影日誌では、物語と別次元の過激な仕事振りと生活振りに驚いた。芸術家の素顔をみるようで実に面白かった。 読了日:11月13日 著者:野上照代,ヴラジーミルヴァシーリエフ,笹井隆男  アメリカの社会主義者が日米戦争を仕組んだ 「日米近現代史」から戦争と革命の20世紀を総括するの感想 アメリカの社会主義者が日米戦争を仕組んだ 「日米近現代史」から戦争と革命の20世紀を総括するの感想アメリカは、1924年の絶対的排日移民法などで人種差別し、オレンジプランなる対日戦争計画も仕上げ、日本を追い詰める態勢に入ったそうだ。国際金融勢力が大統領を操り、国際主義なる社会主義で、中国の共産化を図るため、邪魔な日本の影響を削ぐため、アメリカは日本に戦争をしかけたそうだ。日本は、経済制裁で追い詰められ自衛の戦争に至ったと。現代のグローバリズムも同じことで国際金融勢力の世界支配の一環と。そういうこともあるかもと思うも正直スッキリせぬ読後。 読了日:11月6日 著者:馬渕睦夫  昭和史の10大事件の感想 昭和史の10大事件の感想向島、深川育ちで墨田川高校出身の親子ほどの歳の差のお二人で面白い対談。昭和の感じ方が、戦争体験差によって異なることがよくわかる。昭和64年、昭和というものが人間的にも終わっちゃった。価値観というものの変換点と言う。よくわかる。ただ、終戦でも転換していたと吉村昭は背中の勲章で記していた。青森行きのみじめな列車で、日本人と異なる人種に見える、険しい目、落ち着きなし、老人に席を譲ろうともせず、窓から子に排尿させる女、荒む心と。 読了日:11月5日 著者:半藤一利,宮部みゆき  アメリカの戦争責任 (PHP新書)の感想 アメリカの戦争責任 (PHP新書)の感想有馬哲夫の歴史とプロパガンダでは、ルーズベルトに相応の開戦の責任がある事が明らかになっていた。本書では、引き継いだトルーマンは、ルーズベルトがチャーチルと交わした原爆開発成功時に日本に投下する密約を見直さず、周りに勧められた終戦案をとらず、原爆投下を優先し、一般人民殺害した戦犯と。戦後、犯罪性を逃れるため原爆が終戦を早め多くの命を救ったとのフィクションをプロパガンダしたと。メディアでは聞けない論証だ。 読了日:11月3日 著者:竹田恒泰  杉原千畝: 情報に賭けた外交官 (新潮文庫)の感想 杉原千畝: 情報に賭けた外交官 (新潮文庫)の感想手嶋龍一曰く「情報士官」の名に値する人物であったそうだ。1920年代、1930年代、1941年12月までの激動に外交官として満州、フィンランド、リトアニア、プラハ、ルーマニアと転じて果たした業績には驚いた。一線の知性と情報をいかせぬ日本の中枢部の愚かしさにまたも嘆息させられた。厳しい外交・諜報努力と業績を知るほど、同時に成し遂げられた人道的事績がより崇高に感じられた。 読了日:11月1日 著者:白石仁章  日本嫌いのアメリカ人がたった7日間で日本を大好きになった理由の感想 日本嫌いのアメリカ人がたった7日間で日本を大好きになった理由の感想旬、初の楽しみ、躾、稽古事の意義、商品・サービスを細分化する思いやり発想、つきぬ改良、相手に合わせる文化など、ないがしろにしがちなありふれた旧来の価値観が、日本の力の源泉だと、35年ハリウッドの世界にいた著者が教えてくれた。日本らしさを失わないようにしないと未来も危ういと考えさせられる。楽しい本であったが、最近多い日本自賛番組とは少し違い、忘れんときなさいとの警鐘のような気もした。 読了日:10月31日 著者:マックス桐島  日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る: なぜ、日本企業の防虫蚊帳がケニアでトップシェアをとれたのか?の感想 日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る: なぜ、日本企業の防虫蚊帳がケニアでトップシェアをとれたのか?の感想WHO、国連、TIME表彰、ダボス会議、現地生産、大型商談、ブッシュ見学など、出だしは派手なノンフィクションかと思ったが、すぐにストーリー仕立てのマーケティングのレクチャー本風になり、解説コラムまで登場し、アフリカでのスタートアップの理屈解説も頻繁になる。ノンフィクションとは違う、マーケティングの物語仕立ての事例紹介で、住友化学での伝統的大企業の限界克服活動の紹介でもあった。面白い素材もあるけれど、読むのに疲れる文章、構成だった。推敲したのと言いたくなる文脈もあり編集者の仕事って何だろう。 読了日:10月30日 著者:浅枝敏行  ホンダジェット: 開発リーダーが語る30年の全軌跡の感想 ホンダジェット: 開発リーダーが語る30年の全軌跡の感想全うな技術的野心を実現させた胸のすく物語だ。すばらしい。航空宇宙関係の国際的三賞を世界で初めて受賞した藤野道格、革新機に挑戦させ続けたホンダ。冒険心が心地よい。いよいよ、世界でデリバリーされ、新しいホンダのモビリティーが世界で羽ばたくらしい。創業者の意気が受け継がれ、日本で開発し、アメリカで造るホンダスタイルだ。著者の悲劇の発動機「誉」では中島飛行機の悲劇がやるせなかった。その技術者たちは、後に自動車で活躍し、その自動車会社が、航空機事業に参入する。歳月を経たすごい話だ。日本の進路を暗示するかのようだ。 読了日:10月26日 著者:前間孝則  背中の勲章 (新潮文庫)の感想 背中の勲章 (新潮文庫)の感想岩手県最初の戦死者とされた人物の捕虜となった苦悩、陸海軍の兵の虜囚の屈折、特攻生き残りの生ける死に顔、米の捕虜の処遇、米市民の反応、敗戦による日本人の変節とすさんだ心が、丹念に描かれている。またも、事実で戦争の真実を突きつけられた思いがした。復員し帰郷の列車内で「若い男は疲れた老人に席を譲ろうともせず」「険しい目で落ち着きなし」「日本人と異なる人種にみえる」とあった。以来、70年、そのままなのか。 読了日:10月22日 著者:吉村昭  神宮の奇跡 (講談社文庫)の感想 神宮の奇跡 (講談社文庫)の感想昭和33年が神々しく、清々しく、力の湧き出るような年であったとは、驚きだ。敗戦による命懸けの帰国、前進するのみの困窮生活、勉学とスポーツでの精神鍛錬、野球の試練と歓喜、陛下の誠実な青春、胸に迫った。語られた時代は強靭で健全で誇り高い人々に満ちていた。この熱情と忍耐力は、いまでも列島のそこかしこで燃やされていると思いたい。知られていないだけだと思いたい。 読了日:10月21日 著者:門田隆将  月下美人 (文春文庫)の感想 月下美人 (文春文庫)の感想取材相手との親交を重ねて、過去を封じた闇の安息を壊し、家庭に困惑を招いた小説家としての罪を勤め、過去と向き合って安寧に至る元逃亡兵の人生の変化に安堵する小説家の救われる思いが丁寧に描かれていた。月下美人の一夜の開化が、罪と贖罪と悟りの安寧を表すかのようで凄惨な生き様にも清廉な読後感となった。 読了日:10月20日 著者:吉村昭  帰艦セズ (文春文庫)の感想 帰艦セズ (文春文庫)の感想逃亡の主人公は実在の人物だった。帰艦セズの乗員のいきさつを逃亡の主人公が思いやり、小樽の山中から阿武隈の出港を見下ろす帰艦しなかった乗員の姿を想うシーンの切なさには胸がつまる。 読了日:10月20日 著者:吉村昭  逃亡 (文春文庫)の感想 逃亡 (文春文庫)の感想兵員の孤独、精神の暴力、文字通りの暴力、服従と不服従、規律と狡猾、脅迫と懐柔等の極限での人間の本性が救いを求める姿が描かれている。戦争の綺麗事の精神論の空々しさが一層際立つようだ。 読了日:10月19日 著者:吉村昭  伊四〇〇型潜水艦 最後の航跡 下の感想 伊四〇〇型潜水艦 最後の航跡 下の感想吉村昭の小説を思い出させられるばかりのノンフィクション物語だった。訳者のあとがきによればWSJで「細部までこだわり抜いた興味深い調査と巧みな語り」と、meticulouslyと評されたらしい。著者巻頭言「左右いずれの側から見比べても、本当のことはいつもそう簡単にはわからない」と。相手の事も考えられる著者がアメリカ人であることに少々驚いた。戦争の本質は、依然「藪の中」だが、勇気と忍耐と言うだけでは語りつくせない高潔な物語を心から理解するのは容易ではないとも著者は言う。 読了日:10月18日 著者:ジョン・J.ゲヘーガン  アメリカ人禅僧、日本社会の構造に分け入る 13人との対話の感想 アメリカ人禅僧、日本社会の構造に分け入る 13人との対話の感想対談相手の発言は、実績に裏打ちされた説得力のある行動している者の見事な考えだった。信念と真理が感じられ、教条的な日本のメディア的身勝手話は一切なかった。確実に前進している人々だった。著者の日本らしさの損得をあぶりだそうとする試みは、本人の「日本はやっぱりへんな国」との評で停止かと。唯一13人目の話は何を表現したいのか難しかった。 読了日:10月15日 著者:ミラー和空  一路(下) (中公文庫)の感想 一路(下) (中公文庫)の感想気持ちの晴れる時代劇。自浄できる賢者に未来を託したいとの願いがこもっている気がした。真面目に本分を賢くつくせと、政治、行政、司法に対して言いたいのかもしれない。 読了日:10月13日 著者:浅田次郎  一路(上) (中公文庫)の感想 一路(上) (中公文庫)の感想泰平の世の中で、長い、都合による運用の積み重ねで、本分は忘れられ、しきたりが形骸化し、私利と保身に政治が支配され、経世済民がなされない堕落した社会は、糺せと言っているようでした。抗う人の意志は、体現する行いによって賛同は得られるというようです。面白い。 読了日:10月12日 著者:浅田次郎  どんな仕事でも必ず成果が出せる トヨタの自分で考える力の感想 どんな仕事でも必ず成果が出せる トヨタの自分で考える力の感想トヨタの人と仕事の考え方を物語仕立てで解説した、とっつきやすい気持ちの良い啓蒙書。このような読み手に配慮した本はこれから学ぶ人には恰好だと思う。また、勤めにすり減ってきた人にも立ち止まって見直す時の視点が整理できていると思う。楽しい紹介本でした。 読了日:10月10日 著者:原マサヒコ  伊四〇〇型潜水艦 最後の航跡 上の感想 伊四〇〇型潜水艦 最後の航跡 上の感想地道な資料調査・取材による内容で、巻末の出典の注記はそれを物語るような量。日米どちらにも肩入れしない流れで事績を構成してあり、好印象。残虐行為、無謀行為、英雄行為、愚劣行為等の背景、結末、疑問が整理されていて、惨劇に嘆息しきりだった。倉田耕一著「アメリカ本土を爆撃した男」の戦後の贖罪と和解の美談の記述はなかった。 読了日:10月7日 著者:ジョン・J.ゲヘーガン  二十世紀と格闘した先人たち: 一九〇〇年 アジア・アメリカの興隆 (新潮文庫)の感想 二十世紀と格闘した先人たち: 一九〇〇年 アジア・アメリカの興隆 (新潮文庫)の感想20世紀の歴史を正しく理解ができた気になれた。「若き日本の肖像 1900年、欧州への旅」の姉妹本で、アジア太平洋地域での先人たちの思考の格闘の歴史、その明暗までよくわかった。孫文の「西洋の覇道を模倣し、東洋の王道を否定」との警告に得心。なぜ日本人は威張るのか、優位にたつと傲慢と増長に陥るのか、条理の側に立つ勇気はあるかと、歴史認識の底にあるものが問われている。 読了日:10月4日 著者:寺島実郎  日本人の道具の感想 日本人の道具の感想表紙は、肥柄杓だった。農耕、漁労、生活、祭、防火、灯りなど、生活にかかわる古い道具の写真。素朴な味わいがある。庶民の器用さを物語る品々。 読了日:10月3日 著者:清永安雄  浅田次郎と歩く中山道 - 『一路』の舞台をたずねて (中公文庫)の感想 浅田次郎と歩く中山道 - 『一路』の舞台をたずねて (中公文庫)の感想「一路」の舞台の旅行案内で、現地を歩いてみたくなる冊子。風情が残された背景がよくわかる。中山道は大事にしていきたい歴史街道のようだ。安藤優一郎の解説や、渡邊あゆみ、中村獅童との対談も面白い。 読了日:9月30日 著者:浅田次郎  世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想 世界の辺境とハードボイルド室町時代の感想評判どおり、面白い。著者曰く、「奇書」で「超時空比較文明論」だそうだ。辺境にも中世にも今ここにないものを求めているとしたら、健全な印と言う。とりとめのないような対談集に思えたが、読み終えると失われつつある日本人文明の本質を見せてもらった気になった。よく観察し、その立場になりきって思考されているのに驚いた。実に楽しかった。 読了日:9月30日 著者:高野秀行,清水克行  希望の資本論 ― 私たちは資本主義の限界にどう向き合うかの感想 希望の資本論 ― 私たちは資本主義の限界にどう向き合うかの感想経済学としての資本論の正当性・論理性を思い出させてもらいました。池上さんもマル系専攻大学生だったのですね。佐藤さんは、社青同で珍しい高校生左翼で、アナキズムを探求したくてそれができる唯一の同志社神学部にいって、キリスト教神学にはまったとは驚きでした。肚のすわりが違うはずです。二人の危機感あふれる反・反知性主義に得心しました。「右肩下がりの教育の現状」の未来はとても怖い。 読了日:9月27日 著者:池上彰,佐藤優  歴史とプロパガンダの感想 歴史とプロパガンダの感想著者の「「スイス諜報網」の日米終戦工作」の続きのようで興味深い。同書で藤村義郎中佐の美談は対日プロパガンダのひとつで粉飾と虚偽に満ちたものと論証されていた。本書では、対日プロパガンダが軍国主義と並ぶほどの思想統制、メディア支配、私信検閲であったことが論証され、おぞましい洗脳ぶり。NHKラジオ番組で米軍のブラック・プロパガンダ「真相はこうだ」放送に抗議が多く寄せられ、職員からもあの放送を聞くと悪寒を覚えるとの感想があったそうで少し救われた。後年のキッシンジャー・周・佐藤・田中の米中日の交渉も実に面白い。 読了日:9月25日 著者:有馬哲夫  日本語の科学が世界を変える (筑摩選書)の感想 日本語の科学が世界を変える (筑摩選書)の感想とても面白い。学究の先端の人々はしるよしもないが、地道で果敢に挑む姿と、成し遂げられた偉大な成果が、実は、日本語の科学としての成果であったものが多いと。この観察に未来が明るく感じられました。論文数を競ったり、アイデンティティーのないグローバル化など、百害あって一利なしの現状には未来が曇ります。でもネイチャーも面白い論文が減り、殻を破るようなものは日本人のものとの評に希望湧きます。「日本語の科学はすてたもんではない」とよくわかりました。 読了日:9月23日 著者:松尾義之  海軍乙事件 (文春文庫)の感想 海軍乙事件 (文春文庫)の感想連合艦隊司令長官を二代続けて航空機移動中に失う軍事行動に驚いた。リスク管理と異常事態対応要領は戦略の根底にあるものと今では当たり前に思うが、戦意高揚、俘虜忌避自決の中で、徹底した軍事統制が貫徹していたのかと思っていたが、情報戦においては士気の低下防止の甘い論拠で大失策を繰り返していたようだ。参謀が作戦計画書を破棄せず、紛失しても都合よく解釈運用され、本人は事実沈静化のために栄転し、作戦も暗号も変えず、米軍に蹂躙されていくとは、悲しすぎる。日本人の変わらぬ本質を見せつけられた。見事な作品だ。 読了日:9月21日 著者:吉村昭  大本営が震えた日 (新潮文庫)の感想 大本営が震えた日 (新潮文庫)の感想奇襲作戦の成功を期して懸命に企図秘匿に命を張った人々が描かれ、勝利を賭した姿がとても悲しい。あの惨劇の始まりが懸命な冒険的でも万策を尽くした作戦であったことが、余計に避けきれなかったものなのかとやるせなくなる。 読了日:9月19日 著者:吉村昭  気仙沼ニッティング物語:いいものを編む会社の感想 気仙沼ニッティング物語:いいものを編む会社の感想気持ちのよい健やかな内容でした。震災復興のお題目ではない、地域循環事業の起業話で、調査、研究、設計、調達、人材募集、訓練、受注、製造、納品、宣伝、アフタケアの一連が、地域に根差し、地域に助けられながら、作り上げられる話で、読み易く、楽しい内容。唯一、全国放送メディアの震災復興お涙シナリオでやらせ撮影が要求され、現地の人の逞しく明るく乗り越えようとする素顔との解離に断ったくだりもあり、堕落メディアはここでも有難迷惑をかけてたようです。 読了日:9月15日 著者:御手洗瑞子  切り捨てSONY リストラ部屋は何を奪ったかの感想 切り捨てSONY リストラ部屋は何を奪ったかの感想ブレット・スティーブンスは日本酷評の中で「ソニーは人員整理ができず、NY公立学校の「ラバールーム」で時間を過ごさせている」と。米人は人員整理に疑問はなく、利益至上・高額報酬は正義であり、日本は変なのだろう。今のソニー経営も「倒れゆく巨象IBMはなぜ凋落したのか」の金融経営と同じで、資産・人材の切り売り経営のようだ。「巨象」は株価と役員高額報酬と引き換えに、品質と顧客サービスをないがしろにしてきたそうだが、本書でのソニーも、「巨象」の拝金経営によく似ている気がしてきた。原点回帰するとよいが。 読了日:9月13日 著者:清武英利  もう一つの「幕末史」: “裏側”にこそ「本当の歴史」がある! (単行本)の感想 もう一つの「幕末史」: “裏側”にこそ「本当の歴史」がある! (単行本)の感想反薩長史観はとても面白い。後付けの権力者用語の維新でなくて御一新と呼んだ方がよさそうだ。龍馬暗殺の犯人推定もさもありなんと得心。御一新のときのリアリズム、自己変革、人材登用のダイナミズムが今こそ問われると。昭和戦前史のタコツボエリート集団主義のような官僚主義で国策誤るなと。攘夷でヒステリー起こすたちが日本人には遺伝しているらしい。劇画を見ているかのように面白かった。 読了日:9月12日 著者:半藤一利  狗賓(ぐひん)童子の島の感想 狗賓(ぐひん)童子の島の感想自然と共存しながら強く穏やかに過ごす人々の健やかな描写に心が和みます。支配と収奪と暴力と驕りの歴史にはやるせなくなります。いわれなき咎に忍耐と研鑽と信念と支えあう人々との月日で勝ち抜いた姿に安堵できます。幕府も新政府も支配と収奪の本質は変わらないとの諦観には、経世済民の見識の深さに思い至ります。狗賓童子の島との題にされたことがよくわかりました。島国日本の今も変われぬ姿かのようで、とても面白い作品。 読了日:9月12日 著者:飯嶋和一  日本人が知らない漁業の大問題 (新潮新書)の感想 日本人が知らない漁業の大問題 (新潮新書)の感想従来の流通制度の効能を改めて再評価し、大規模で規格化したグローバルな流通の批判が繰り返しされ、美味しい魚を味わいたい人の為に少し考え直せと言います。豊かな漁場に恵まれているのに、安くて不味い鮮度の落ちる魚食事と。それにしても本書で言う問題点があるのに、なぜにこんなに愚かしいのか、漁業者、漁協、流通、消費者、行政、学者とも、自分ベストで批判や提言主張はするが、すくんで前にでられないかのようだ。近海「漁業消滅」もさもありなんと心配になった。 読了日:9月10日 著者:佐野雅昭  日本の「運命」について語ろうの感想 日本の「運命」について語ろうの感想近代の事績の由来が数多く解説されていて面白い。江戸の大名の生活基底にある事実、明治維新の志士の本音、中国の歴史の懐深さ、植民地進出の事情と西欧と異なる殖産統治など本質的なことが分かり易い。科学は経験の累積で確実に進歩をとげるが、人類もそれにともなって進化していると思うなと。変容、あるいは退行していると思うくらいでないと正しいものは書けないと。やはり、事実を曖昧にしない姿勢を守っている人だ。 読了日:9月6日 著者:浅田次郎  熱風の日本史の感想 熱風の日本史の感想面白い。明治から平成までの日本人の付和雷同、変節、社会の風潮がよくわかる。新聞が扇動し、庶民がますます踊り、また、庶民が排他されてもきたのが実像のようだ。著者は熱風(同調)現象をまとめ日本人の自画像を描いたらしい。それにしても新聞は、いわばバブル商売人で、右でも左でも時々の大勢に逆らわず正義ぶって、泡立てれば泡立てるほど儲かるとばかりにしてきたらしい。「度し難き厚顔無恥(1945.8.18高見順の評)」らしい。 読了日:9月5日 著者:井上亮  陸奥爆沈 (新潮文庫)の感想 陸奥爆沈 (新潮文庫)の感想吉村昭自身も小説と言うより、ドキュメンタリーの範疇に入るのだろうと評していました。不気味で堅牢で近寄りがたい威風をたたえる戦艦の中に、人間がひしめきあい、規律に服従する世界にも欲望や恨みがひそんでいることが書き明かされていました。はかなさと同居する悲しみがこみ上げてきます。日本海軍の底で生きた兵士の現実が浮かび上がってきたように思います。 読了日:9月4日 著者:吉村昭  大放言 (新潮新書)の感想 大放言 (新潮新書)の感想大手新聞の扇動的な商業記事への反論がよくわかった。正直なわかりやすい説明。炎上史で、大方の人間は、新聞資本の自己都合偏向角度体質に気付くのでは。政治家、新聞記者がおかしい国は、おかしくなる。図書館の民業圧迫もよくわかる。娯楽系の新刊は一年は図書館に入れるなというのも一理ある。メディアの皮層な正義きどりの暴きも痛快。 読了日:8月30日 著者:百田尚樹  戦艦武蔵ノート (岩波現代文庫)の感想 戦艦武蔵ノート (岩波現代文庫)の感想面白く読みました。吉村昭の戦争観、戦争と敗北についての民衆の考えに対する評価、進歩的文化人の言説への懐疑、戦争批判にみえる卑怯な態度、開戦の責任、物を対象にした文学小説創作への不安、事実の直接取材の信念、他人の書いたものへの不信などなど、あの小説を創り上げるにいたる吉村昭の素顔をみたような気になった。ノンフィクションの宝。 読了日:8月30日 著者:吉村昭  水木しげる: 鬼太郎、戦争、そして人生 (とんぼの本)の感想 水木しげる: 鬼太郎、戦争、そして人生 (とんぼの本)の感想とても懐かしく面白い。梅原猛との2010年の対談、呉智英の解説では、水木しげるの魅力を改めて知る思い。紹介される戦前、戦地、戦後の絵には、健やかなもの、暗く寂しいもの、温もりが溢れるものが、同居しているようで心に残る。資料の蒐集、勉強の片鱗には感服至極。呉によれば、漫画家は手塚治虫の影響を受けているが、水木は全く受けておらず、劇画グループとの接点はなく、非常に特異な存在だそうだ。紙芝居、貸本、雑誌と漫画の三世代を生きた人はいないそうだ。網羅する復刻が出てるようで楽しみだ。 読了日:8月29日 著者:水木しげる,呉智英,梅原猛  骨が語る日本人の歴史 (ちくま新書)の感想 骨が語る日本人の歴史 (ちくま新書)の感想日本人の起源が多系統で独自の発展を遂げたり、外来文化の影響を受けたりしてきたことがよくわかった。骨の分析で証され、これまで流行って来たルーツ論議の独善さがよくわかった。身体特徴の変わり具合には驚いた。遺骨で生き生きした人の様子が分かるとは不思議なものだ。 読了日:8月26日 著者:片山一道  世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠の感想 世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠の感想ノーベル賞経済学者が、アメリカの政治と政策の失敗を糾弾したまとめ本。不平等は市場ではなく、政治がつくったと。銀行は投機ビジネスをやめ、貸付業務に戻れと。上位1%の税率が貧困層より低いと。キャピタルゲイン課税も低いと。当たり前に増税せよと。トリクルダウンは幻想、中間層以下の消費が需要を作ると。アメリカに機会均等はなし。取り戻せ。チャールズ・ファーガソンの強欲の帝国と同意見。サマーズのようなハーバード経済学者達は強欲略奪者セクト。149億ドルの商業農家への補助金も呆れる。貧者から収奪し富者へ分配の国。 読了日:8月21日 著者:ジョセフ・E・スティグリッツ  田園回帰1%戦略: 地元に人と仕事を取り戻す (シリーズ田園回帰)の感想 田園回帰1%戦略: 地元に人と仕事を取り戻す (シリーズ田園回帰)の感想田園回帰世帯を増やし、過疎の中山間地の就労人口を増やし、生産と調達の地域内循環量をふやし、生活圏として過疎地を改造するやり方がよくわかった。地域の自覚と工夫次第で過疎地に埋まっている遊休財が活かされ、地域は生き返ると。分析、手法、事例とも納得できる実践的なもので、人口収縮国家に萎縮するのは間違いのようだ。但し、著者の文明観から産業文明、都市文明の批判が繰り返され、説得力のある実践良書なのにかえって、田園生活の敷居が高くなる。田園いいねで十分皆わかるのでは。 読了日:8月19日 著者:藤山浩  ブラック オア ホワイトの感想 ブラック オア ホワイトの感想現役を終えた男が、自分自身が祖父、父から繋がっていたことを自身に理解させ、自身の現役生活を自身に理解させようとするかのような話でしたが、老境に入ろうとして現役から遠ざかる時、それまでに過ごしてきた時と場所を辿りながら、最期の自分を突き詰める心境になる話でした。斜に構えた夢うつつな語り口に、突き詰めて生きてきたはずの戦後世代の浮沈を込めているのかと思います。 読了日:8月16日 著者:浅田次郎  「スイス諜報網」の日米終戦工作: ポツダム宣言はなぜ受けいれられたか (新潮選書)の感想 「スイス諜報網」の日米終戦工作: ポツダム宣言はなぜ受けいれられたか (新潮選書)の感想中田整一のドクター・ハックに感動しましたが、アメリカの中枢にも親日家がいて、天皇制存続と国体維持、早期終戦を画策していたとは驚きました。トルーマンの原爆投下の野心が、使える機会作りと防共の対ソ威嚇にあったとは・・・京都を原爆投下第一候補地からはずしたのは、長老の米陸軍長官であったとは・・・藤村海軍中佐の美談はフィクションで戦後はCIA関係人であったとは・・・惨劇収束に向けて懸命な米国要人もいたことに驚きました。 読了日:8月12日 著者:有馬哲夫  居酒屋の誕生: 江戸の呑みだおれ文化 (ちくま学芸文庫)の感想 居酒屋の誕生: 江戸の呑みだおれ文化 (ちくま学芸文庫)の感想18世紀の中頃、百万都市江戸の居酒屋が、都市生活者の息抜きとして今の居酒屋にも繋がってることがよくわかりました。豊かな肴、大量の下り酒の消費、工夫凝らした呑み方、酒具、いきいきとした古文書の呑兵衛達の挿絵などなどとても楽しい。ひとり酒、割り勘、定額メニュー、夜明かし、むかえ酒など、遊ぶ庶民の活気が満ちた本で大変面白い。 読了日:8月11日 著者:飯野亮一  答えは必ずある−−−逆境をはね返したマツダの発想力の感想 答えは必ずある−−−逆境をはね返したマツダの発想力の感想連続赤字の苦境から見の覚めるような車を立て続けに出して、独自の高性能な世界を造り始めたマツダ。倒産寸前に追い込まれた末の奇跡なのか、何が起きたのか不思議でした。本書でよくわかりました。企業体質の改革に取り組んでいたのですね。日本の縮図をみるようで、マツダのような変革が日本自身に必要で、できるリーダーを選ばねばいけないようです。電気自動車の社会経済的矛盾の指摘に納得です。普及は無理と。 読了日:8月7日 著者:人見光夫  HARD THINGSの感想 HARD THINGSの感想とても全うな経営指南と思います。シリコンバレーのベンチャー企業の思考と行動の規範に感心します。造り、試し、直し、売ったり買ったり、雇ったり解雇したり、借りたり貸したりの荒波の中で、人(同志)と技術製品の成功に最大価値を置いていたようでまともです。チャールズ・ファーガソンの指弾する強欲金融族の対極にあるかのようです。健全で過激で筋の通った実業家伝と思います。著者の「アーンスト&ヤングには恨み骨髄」との評にはさもありなんと。 読了日:8月6日 著者:ベン・ホロウィッツ  新・観光立国論―モノづくり国家を超えての感想 新・観光立国論―モノづくり国家を超えての感想デービット・アトキンソンは、独り善がりの「おもてなし」「技術大国」など自画自賛して、ご都合主義で効率の悪いのが日本で、人が多いから経済規模が大きくなっただけで、これからは観光産業でもっと食えるようにしろと。観光資源の文化財を大事に保護しろと言っていた。本書は、農業、工場、自然、医療など地域に在るものを組み合わせて統合リゾート観光にしてけば、地方でも稼げて、サービス業の低所得も向上できると。それをする人材を育てよと。都市と地域連携の創生の提言だった。 読了日:8月4日 著者:寺島実郎,一般財団法人日本総合研究所  紛争解決人 世界の果てでテロリストと闘うの感想 紛争解決人 世界の果てでテロリストと闘うの感想稲盛さんが、中東問題は貧困問題だと言われ、ダボス会議は成金の会議と評していたようなおぼろげ記憶がある。まさに、米欧による収奪と米欧自国内での権勢の為に使われた"正義"の打算がよくわかった。 読了日:7月30日 著者:森功  殺人者はいかに誕生したか―「十大凶悪事件」を獄中対話で読み解くの感想 殺人者はいかに誕生したか―「十大凶悪事件」を獄中対話で読み解くの感想暴力的生育環境により抑止の効かぬ凶悪性が醸成蓄積され、放置されたままであると、最悪の結果となる事が説明されていた。裁判は量刑を決めるところで、原因究明、再発防止を発信しないところであるそうだ。量刑も弁護士と検事の競い合いの勝敗として決まり、勝敗に固執する価値観に支配されたのが司法の現実らしい。瀬木比呂志の言を思い出した。 読了日:7月26日 著者:長谷川博一  トランクの中の日本―米従軍カメラマンの非公式記録の感想 トランクの中の日本―米従軍カメラマンの非公式記録の感想1995年発刊で20年たつ。70年前の国家の惨劇と日本人の苦難がひしひしと伝わる写真の数々。米軍の記録をとる軍曹が私的にとった写真だそうだ。秘蔵45年間の月日をかけて米国で公開を決心したものだそうだ。戦争がもたらすものの本質を正しく理解しようとし続けねばいけないという気になる、厳粛な写真の数々。 読了日:7月25日 著者:ジョーオダネル  蒼海に消ゆ 祖国アメリカへ特攻した海軍少尉「松藤大治」の生涯 (角川文庫)の感想 蒼海に消ゆ 祖国アメリカへ特攻した海軍少尉「松藤大治」の生涯 (角川文庫)の感想数奇な運命に果敢と挑み、全うした有為の青年の実話で、凛々しく、賢く、優しく、向学心に富む文武の青年像を知った時、太平洋戦争を指揮し、扇動した者に対してのやりばのない憤りが再びこみ上げる。珠玉の人材をも使い捨て、多くの兵士や民を餓死させた参謀達の罪の深さははかりしれない。8月に読むべき本のひとつと思う。 読了日:7月24日 著者:門田隆将  耳鼻削ぎの日本史 (歴史新書y)の感想 耳鼻削ぎの日本史 (歴史新書y)の感想古代から近世までの刑罰から見た社会史で日本人の歴史の素顔をみるようで大変興味深かった。死刑に準ずる罰の用意、女人と僧侶は男と違う別処断、論功証跡の代用証跡としての重宝、懲罰付加で濫用、封建制安定で禁止へと続く利用目的の変遷に、日本の歴史の実相を見るようでした。残酷さの必然性に図らずも得心させられた次第。 読了日:7月22日 著者:清水克行  村上海賊の娘 下巻の感想 村上海賊の娘 下巻の感想とても面白い船戦の物語でした。泉州の気質の源流をみるようでした。躍動あふれる活写の連続で著者の人気のほどがよくわかりました。 読了日:7月20日 著者:和田竜  ローマ法王に米を食べさせた男 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか?の感想 ローマ法王に米を食べさせた男 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか?の感想限界集落と農業の振興を知恵と交渉と実践と説得で成功させた記録で、とても嬉しい物語でした。地方消滅、寺院消滅と突きつけられている未来ばかりでもないなという気になってきます。木村秋則さんが共鳴・協力すること、農地も人も活力を取り戻していくことが、自然の成り行きに感じられます。公務員でもあり僧侶でもある著者の人格にも感服します。とても気持ちのよい格闘記でした。 読了日:7月17日 著者:高野誠鮮  村上海賊の娘 上巻の感想 村上海賊の娘 上巻の感想豪胆な人物の痛快な物語は期待通り。史実の説明もほどよく楽しめる。劇画をみるようですかさず下巻に。 読了日:7月17日 著者:和田竜  国境のない生き方: 私をつくった本と旅 (小学館新書)の感想 国境のない生き方: 私をつくった本と旅 (小学館新書)の感想教育と本の大切さを自身の体験から訴えています。著者ののびやかな、冒険的、すこやかな人生観は、とても気持ちの良いものです。子の解決能力を体験的に鍛えた母堂の教育の仕方への著者の感謝と称賛があふれています。育てるのでなく、力を試す機会を設けて自ら育つ教育を心がけることを説いています。披露される率直な考え方と行動は気持ちの良いものでした。すこぶる健全です。 読了日:7月13日 著者:ヤマザキマリ  「ドイツ帝国」が世界を破滅させる 日本人への警告 (文春新書)の感想 「ドイツ帝国」が世界を破滅させる 日本人への警告 (文春新書)の感想ユーロ圏の政治的理念が経済的な不均衡の前に難渋している様子がとてもよくわかった。東欧のソビエト時代に教育された質の高い労働力を低賃金で活用し、自国内の賃金も抑制して、ユーロ域内の貿易黒字を稼ぎだす、「ドイツ帝国」。規律重視、権威主義、家父長的社会システムが、自由と平等と個人主義の南欧諸国を支配し、仏をも隷属させているそうだ。金融資本主義の核戦争にかわる脅威がヨーロッパ格差社会を覆いはじめたと。エーゲ海の怒りも一理あるらしい。 読了日:7月12日 著者:エマニュエル・トッド  寺院消滅の感想 寺院消滅の感想高齢化、少子化、地方消滅の中で、地域にねざした寺院も人口動態の影響をもろに受け、更に、檀家、家、先祖との関係の希薄化でより一層衰退していくと言います。人口動態以上の要素もなぜあるのかよくわかりました。幕府の戸籍行政協力、国教化、高利貸しで地主化、廃仏毀釈、世俗化、戦争協力、農地改革で丸裸、副業兼業、経世済民模索ととてもよくわかりました。良書です。 読了日:7月11日 著者:鵜飼秀徳  日本国最後の帰還兵 深谷義治とその家族の感想 日本国最後の帰還兵 深谷義治とその家族の感想大地の子、ワイルド・スワン同様の衝撃でした。専横、迫害、差別、虐待のすさまじさ、それを耐え抜いた気骨、忍耐、家族愛、同胞愛に圧倒され、いくどもこみ上げてきます。本書は、忘れられている歴史をとどめると同時に、資本主義国日本での苦悩と勤勉と親孝行の証でもあるようです。みごとな読みごたえがありました。 読了日:7月8日 著者:深谷敏雄  鉄道技術の日本史 - SLから、電車、超電導リニアまで (中公新書 2312)の感想 鉄道技術の日本史 - SLから、電車、超電導リニアまで (中公新書 2312)の感想鉄道先進国になるまでの歴史がよくわかった。営々と学び、造り、営繕してきた鉄道は、総合産業で技術文化でもあるようだ。西洋に遅れること40年の日本が、今や、世界有数の鉄道網、製造企業群、鉄道事業者を抱えるまでなれたことは日本の有力資産だ。新日鉄住金の車輪や車軸の競争力、日立製作所の培ってきた総合システムとしての鉄道構築力、イギリスでの事業化受注ともに力強い。140年前にイギリスに教えを請い、学び、イギリスで製造・運営するまでになった歴史は目を見張るものだ。これからも楽しみだ。 読了日:7月6日 著者:小島英俊  文庫 悲劇の発動機「誉」 (草思社文庫)の感想 文庫 悲劇の発動機「誉」 (草思社文庫)の感想堀越二郎の零式艦上戦闘機のエンジンに三菱ではなく中島飛行機の栄エンジンが終戦まで使われ、数多くの悲劇を運んだ歴史があるが、後継機の高性能エンジン誉が若い学卒技術者に託され、開発、試作の後、繊細すぎて実用に耐えず、品質劣化のまま、実戦配備され、故障多発、保守繁忙で国力・生産力浪費の悲劇が繰り広げられていたとは・・技術・生産を戦略的に判断できる将官が皆無に近かったとは・・現代の技術人には心配はないのだろうか。 読了日:7月3日 著者:前間孝則  資本主義の終焉と歴史の危機 (集英社新書)の感想 資本主義の終焉と歴史の危機 (集英社新書)の感想16世紀の低金利時代の及ぼした社会革命と、現代の低金利時代のアナロジーで、面白かった。もはや外に蒐集できる周辺はなく、自国内で格差つけて蒐集して利益だすしかないのが、現代の資本主義だと。処方は、今の状態を維持して定常社会、更新社会にして、脱成長という成長をしてれば、次の社会システムがみつかるだろうと。言いっ放しでした。 読了日:6月29日 著者:水野和夫  コンテンツの秘密―ぼくがジブリで考えたこと (NHK出版新書 458)の感想 コンテンツの秘密―ぼくがジブリで考えたこと (NHK出版新書 458)の感想ネットで参加型コンテンツ披露空間を実用化した著者が、コンテンツ製作の最先端の創造行為を情報処理の視点で解説してくれる。興味深い。摩訶不思議なジブリの世界のつくられ方が、脳での情報処理の動きとして解説してみせるが、そうは言っても、結局、蓄積された主観、取捨された記憶と、長年磨いてきた表現技能が組み合わさってもたらされる創造行為で、コンテンツは限られた人の技の賜物と改めて感じた次第。 読了日:6月28日 著者:川上量生  世界の未来は日本次第の感想 世界の未来は日本次第の感想本書でも実態例の説得力に感服です。重工業の日本の力は日本のメディアではわかりませんが、著者の長年の観察に驚くばかりです。韓国、中国の実相も生産現場で起きている事例で端的に推察ができ、そうなった価値観、国民性を正しく理解できた気がします。二国の破滅的未来予測は必然のようです。英国の国際力、金融力の源泉もよくわかりました。日本を安売りせず、知恵とシステムを高く売るのが懸案で、できない話ではないようです。日本は否応なく特異な分野で先端を走り続けなければ生き残れない宿命のようです。 読了日:6月28日 著者:長谷川慶太郎,渡邉哲也  日本インターネット書紀 この国のインターネットは、解体寸前のビルに間借りした小さな会社からはじまったの感想 日本インターネット書紀 この国のインターネットは、解体寸前のビルに間借りした小さな会社からはじまったの感想ISPの立ち上げの志士伝に心が揺さぶられるようでした。苦難の末の開業、邁進、飛躍、資金調達、頓挫、転換、再起とつづくめまぐるしい技術の商用化の業績に圧倒されました。支えたのは信念と技術探求熱と公徳心と愛国心と体力と知力と同志であったようです。遅滞行政と学閥との格闘の歴史もあったとは。あの勝栄二郎が社長になった背景がなんとなくわかりました。 読了日:6月25日 著者:鈴木幸一  ふしぎなイギリス (講談社現代新書)の感想 ふしぎなイギリス (講談社現代新書)の感想「ふしぎな国道」と似た題名で、英国価値観の不思議さがよくわかりましたが、実は、united kingdom of ...は、現実的で民主的で伝統的で妥協的で、尚且つ、変革的で寛容でもあって、ふしぎな優雅な洗練された階級社会、王室と国民と議会の議論と対立と親愛の三角関係、不道徳と許しの再生社会、歴史と民族の尊厳を守る社会と、なんとも奥深い。成長あり、原発新設あり、大量移民あり、暴動あり、国家分裂投票決着となんともすごい。 読了日:6月23日 著者:笠原敏彦  日本木造遺産 千年の建築を旅するの感想 日本木造遺産 千年の建築を旅するの感想日本の引き継がれてきた木造建築の素晴らしさに驚きました。信仰、防衛、統治、庶民生活、貴族生活、茶道等の用途で作られてきた木造建築物が多様な表情をもっていてとても面白い。著者曰く、遺跡ではなく、たゆまぬメンテで過去の実物を現代に見せ、今後も生き続けさせることができるいわば現代建築で、未来の建築でもあるそうです。近代建築では味わえない精神性が迫ってくるものばかり。是非、実物を見たいと思う。 読了日:6月20日 著者:藤森照信  世界を動かす技術思考 要素からシステムへ (ブルーバックス)の感想 世界を動かす技術思考 要素からシステムへ (ブルーバックス)の感想プロダクト単体に固執してプロセスのスコープを吟味せず、的はずれの性能に自己満足して社会経済から遊離して漂い始めた技術者と学者と技官が多かったのか?日本の弱点は技術の実戦投入の実証吟味、兵站、運用の科学的立案が劣っていることは知っていた筈ではなかったのだろうか?と思ってしまう。 読了日:6月18日 著者:木村英紀  はじめての福島学の感想 はじめての福島学の感想浅はかな風潮、上滑り善意、はた迷惑への啓蒙書でした。大手新聞社等マスコミ、タレント学者をうさん臭く感じる一般人に理解しやすいデータと整理した情報を提供してくれる本。正しい理解がやっとできた気になる。但し、これを読んでもわかったような気になったり、思考停止したりせんでねと著者に言われてるような好書でした。 読了日:6月16日 著者:開沼博  田園発 港行き自転車 (下)の感想 田園発 港行き自転車 (下)の感想瑞々しい舞台と再生の人生模様がとても気持ちのよいものでした。苦難や過ちを経ても心を込めて守りきる清々しい生き方が歌い上げられていました。風土と精神の健やかさが保たれている救われる物語でした。 読了日:6月13日 著者:宮本輝  人生をいじくり回してはいけない (ちくま文庫)の感想 人生をいじくり回してはいけない (ちくま文庫)の感想達観した幸福観、地道な経済観、のんびりした勤労観、努力した自負、努力に見返りを求めすぎない生活観と、いろいろ振り返えさせられます。妖怪と土人を愛する人が、ゲーテを愛読した青年であったとは。 読了日:6月13日 著者:水木しげる  田園発 港行き自転車 (上)の感想 田園発 港行き自転車 (上)の感想富山の入善、滑川、京都の宮川町、東京が舞台で、それぞれの生活のなかで黒部下流の田園の風土、気質に回帰している穏やかな心情が描かれている。清丸惠一郎の北陸資本主義で書かれている気質と風土がよくわかる物語。下巻でのそれぞれの過去から未来への人生の踏み出し展開に期待。 読了日:6月8日 著者:宮本輝  さっさと不況を終わらせろ (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)の感想 さっさと不況を終わらせろ (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)の感想チャールズ・ファーガソンのPredator Nationも2012年刊で、悪事の告発書でしたが、本書は、悪事による危機発生の解明と不況脱出処方箋でした。犯人は、金融規制の箍をはずした民主・共和の歴代政治家、不良債権を優良と偽り乱売した銀行・証券、偽AAA乱発した格付け会社と同じ結論。本書の建設的不況克服具体策の論述はとてもわかり易く、読み易い。日本は、忠実に実行してて結果を見守られてるのがよくわかりました。御用学者、評論家を一刀両断でした。 読了日:6月5日 著者:ポール・クルーグマン  日本海海戦 悲劇への航海 (下)―バルチック艦隊の最期の感想 日本海海戦 悲劇への航海 (下)―バルチック艦隊の最期の感想坂の上の雲でもロジェストヴェンスキーの苦悩を知りましたが、ロシア人の書いた本書で情状がよくわかりました。皇帝への忠誠、官僚や貴族の堕落への嫌悪、だらしない将官への怒り、軍人としての気骨等々の複雑な苦悩がもうひとつの悲劇であると作者はいいたいのでしょう。捕虜の尊厳を守る対応、東郷の見舞い、シベリアでの革命気運の熱烈歓迎、家族愛、司令官として自分に課した責任の取り方、みごとなロシア軍人の物語でした。救いようのない堕落した時代に格闘した軍人像は、坂の上の雲を見上げる軍人の後の時代にやってくる境遇かも知れません。 読了日:6月2日 著者:コンスタンティン・プレシャコフ  日本海海戦 悲劇への航海 (上)―バルチック艦隊の最期の感想 日本海海戦 悲劇への航海 (上)―バルチック艦隊の最期の感想110年前の海戦の記録。ロシア人による海外資料に基づくとのことわりあり。バルチック艦隊自体の内部崩壊状況が帝、貴族将官、官吏の愚作、保身、権勢欲、汚職によってもたらされたことが描かれ、戦う前から敗戦を覚悟していた司令官の苦悩が描かれています。苦悩しながらも英雄的息抜きはしていたそうでお盛んです。上巻は、帝国を崩壊させた貴族政治と実戦歴のない軍事官僚の姿がよくわかります。日本は世界と丁々発止の国際政治ができていたように思えます。 読了日:5月31日 著者:コンスタンティン・プレシャコフ  北陸資本主義の感想 北陸資本主義の感想内発的な発展をせざるをえなかった北陸地方、「裏日本」の歴史的、文化的事情に納得。収奪され、忍耐する歴史が、教育と努力と創意と紐帯に励む気質になり、明治以来の傾斜配分の最後尾でも北陸新幹線を得て、「裏日本」差別からの飛躍に期待が膨らむそうです。郷土への親愛に溢れる気持ちの良い本。著者は、北陸三県の幸福度が1位から3位を占めるのは、不思議、それほど日本は不幸なのかと。多々ある地の利に優れ、資本も優遇された地の人々が、それらに恵まれてこなかった地域より幸福に感じないのは確かに変だ。 読了日:5月30日 著者:清丸惠三郎  東京劣化 (PHP新書)の感想 東京劣化 (PHP新書)の感想地方消滅では出生率の低下は原因不明と。本書は人口急減原因は年間死亡者数の急増・戦前国策で出生数増加の世代が死亡年齢到達と言う。人口高齢化の原因は、1950年の優生保護法改正での産児制限が不必要に長引いたからと。欧米はベビーブームは10年から20年続き、団塊はなく、人口動態に急峻なカーブがないと。日本はこの二つの人口政策で後の世代に災禍を及ぼしたと。避けられず。財政、税制、年金、福祉、自助、都市基盤、住宅基盤を身の丈に合った形にせざるをえずと。その方策ありと。実に明快。万事の起点にせねば・・・ 読了日:5月27日 著者:松谷明彦  ゼロ・トゥ・ワン―君はゼロから何を生み出せるかの感想 ゼロ・トゥ・ワン―君はゼロから何を生み出せるかの感想ジョージ・パッカーの綻びゆくアメリカでのイメージは、フェースブックの投資で10億ドル超儲けたベンチャー・キャピタリストで、リバタリアンで同性愛者でスタンフォード卒の弁護士だったがウォール街にいち早く見切りをつけ、起業家に。未来を信じず「テック・スローダウン」でインターネットの効能に懐疑的。複雑な人物イメージ。本書では、学生向きの起業講義なので、極めて全う。健全で本質的。浮利を追う金融や起業家を戒め、世の中を見つめなおして、自分の頭で考えて、新しい未来・プロダクトの創造に人生賭けてみろと。とても良い講義。 読了日:5月26日 著者:ピーター・ティール,ブレイク・マスターズ  愛国論の感想 愛国論の感想不愉快で関わりたくないテーマを明快軽妙に議論してくれて読み易かったです。隣人に嫌われ、疎まれ、憎まれるのは悲しいことですが、世界各地で先祖までいわれなき内容で批難されれば、無視する訳にもいかず、反論して情報戦に勝てとお二方とも言われます。子孫のためにも、隣人本人のためにも正しく説くべきと思います。本書で振り返ると民主党政権の拙劣や、朝日新聞の捏造史にはやはりあきれます。他国は右も左も愛国心は変わらないと。日本は愛国心のない似非文化人が多いそうです。 読了日:5月24日 著者:田原総一朗,百田尚樹  辞書になった男 ケンボー先生と山田先生の感想 辞書になった男 ケンボー先生と山田先生の感想大正人の信念と気骨を貫いた一生、作り上げた辞書は渾身のできばえであることを知り感銘しました。情念と反骨と世間に対する責任感がこれほどに込められた国語辞書を持つ国であることがなんだか嬉しくも。言葉を説明することが、時勢や境遇の違う人や世代を繋ぐことであることがわかります。日本は、様々な考え方を表裏に亘って知れる辞書が身近にある国だったのですね。有難みを知りませんでした。辞書は堂々めぐりと思ってましたが、この辞書なら学んだ世代はしっかりした考えになるのではないかと思えます。いい本でした。 読了日:5月23日 著者:佐々木健一  ゴルバチョフが語る 冷戦終結の真実と21世紀の危機 (NHK出版新書 455)の感想 ゴルバチョフが語る 冷戦終結の真実と21世紀の危機 (NHK出版新書 455)の感想25年前に冷戦を終結させたのは、露米欧の首脳同士が相互理解に努力した賜物と。話し合い妥協点を探り合意する努力を、レーガン、ブッシュ、ミッテラン、コール等は惜しまず。相互に事情立場を斟酌しての成果。その後、東西協調の成果を、米欧は勝利と思い込み、ロシアの市場経済導入を弱体化させ、ロシア経済は壊滅的状態に。石油で自力で立ち直り、米のテロとの戦いをロシアは支持もしたが、米は反対するロシアを無視してイラク侵攻。ロシアの米への信頼感は潰える。ゴルバチョフはプーチンのクリミア対応を評価。ロシアにも情状があると。 読了日:5月21日 著者:山内聡彦,NHK取材班  撤退するアメリカと「無秩序」の世紀ーーそして世界の警察はいなくなったの感想 撤退するアメリカと「無秩序」の世紀ーーそして世界の警察はいなくなったの感想タイラー・コーエンは「大格差」で、人工知能を駆使した生産拠点が北米にリショアリングして、資源と軍事力と技術力と資本を力に21世紀は北米の世紀になり、15%の富裕層とそれ以外の所得の増えない層に二極化すると予言してますが、本書もアメリカ以外みんなあてにならず(特に日本は世界一の老齢国で衰えると)、自由と民主主義を踏みにじる権威主義のロシア、イラン、中国に対抗できるのは米国だけで、オバマの弱腰を止め、軍拡すべしと。貧困とか飢餓に著者は関心がないようで、軍事力で世界の警察になって取り締まれと言います。やれやれ。 読了日:5月19日 著者:ブレット・スティーブンズ  国境の人びと: 再考・島国日本の肖像 (新潮選書)の感想 国境の人びと: 再考・島国日本の肖像 (新潮選書)の感想日本の経済水域や領海の起点となる離島が99あって、そこには海上保安官は一人もおらず、多くが廃れ始めていて外国からの収奪にさらされているのが現実らしい。島を守るとは島民の生活を維持することで、島民の生活事実が安全保障の基礎との主張。なぜ、過疎化、廃村化してきたのか。ご都合主義の行政、お人良しな国策、生活優先にならざるをえない庶民、軍事への嫌悪などのようです。周辺国は勢力拡大に邁進していて、もう、待ったなしと。こうなるまで宝をいかせていない現実話に気が滅入るようでした。 読了日:5月16日 著者:山田吉彦  沖縄返還と通貨パニックの感想 沖縄返還と通貨パニックの感想沖縄返還の激動の歴史の中で、ニクソンによって突如もたらされた変動相場制への切り替え。庶民の生活と沖縄経済に打撃となるドル切り下げ、円切り上げ、投機勢力侵入に対して沖縄の行政の志士達がどのように対応したのか、日本の閣僚、省庁がどのように支援や傍観をしたのかが活写されている。米軍支配の中で秘密裏に沖縄の人々の資産毀損を防いだ信念の強さ、深さがどれほどのものなのか、沖縄で生活してきた人にしか推し量ることはできないのかもしれない。著者の憤りが満ちた本であった。 読了日:5月13日 著者:川平成雄  帳簿の世界史の感想 帳簿の世界史の感想簿記会計の二面性(善と秩序の道具、不正と腐敗の手段)が歴史的に繰り返し出現してきたことに納得。騙して奪って儲ける行動性向が西洋文明の歴史的性根と痛感。戦費で国家財政逼迫、国債で借金財政、貴族の課税逃れと富の独占、市民へ重課税、新大陸事業の粉飾バブル崩壊(英の南海会社、仏のミシシッピ会社)、会計改革への抵抗勢力、粉飾決算などなど。20世紀から起きた大恐慌、リーマンショック、巨大経済事件は、14世紀から犯されてきた筋金入りの悪事体質の繰り返しに思えてきます。著者も今の金融システムには希望を失っているようです。 読了日:5月9日 著者:ジェイコブソール  江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統 (星海社新書)の感想 江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統 (星海社新書)の感想現代の世俗に不満を抱く昭和一桁世代の人間が江戸風俗を騙って世相批判した大量の愚痴話を、道徳的教材商品にしたてあげて利用した者がいるとは驚きです。読売はじめ朝日も日経も取り上げ、大手企業も真に受けて社員教育教材にし、挙句の果てに文部科学省も道徳本に盛っているそうです。内容が都合が良いからと虚偽の歴史事実を使って道徳を教えるなどファシズムと同じと。マスコミに踊らされずひろく本を読んで自分で判断できる力がますます必要なようです。 読了日:5月7日 著者:原田実  常磐線中心主義(ジョーバンセントリズム)の感想 常磐線中心主義(ジョーバンセントリズム)の感想常磐地方は、首都圏、ひいては日本に対して、電力のみならず、農産物、工業製品、水産加工品などの大量流通品を供給し続けてきた重要地域であることを再認識。石炭に始まり、米、野菜、海産品まで一世紀以上に亘り供給している自負と、震災、津浪、原発爆発事故、放射能汚染で見失う誇り・・・。郷土愛とどのように折り合いつけていくのか、常磐地方の複雑な心が語られるとても良い本でした。 読了日:5月3日 著者:五十嵐泰正,開沼博,稲田七海,安藤光義,大山昌彦,沼田誠,帯刀治,小松理虔  強欲の帝国: ウォール街に乗っ取られたアメリカの感想 強欲の帝国: ウォール街に乗っ取られたアメリカの感想不動産屋、住宅ローン会社、銀行、格付会社、保険会社が、借金して家を買えば住宅値上がり益で儲けられると市民を騙し、バブル破綻するまでに奪い合い、自分だけ破綻を売り抜けようと、犯した悪事の数々。育てて儲けず、騙して奪って儲ける寡占金融勢力の本性が糾弾され、悪辣さにうんざり。買収された政党、閣僚、学者、有名大学の結社ぶりにはお先が真っ暗。オバマは金融勢力の悪人をひとりも訴追せず、制度もチェンジしないで支援者をだまし、重要な点で国を裏切ったが、米国で得られる悪の中では一番ましと。米国の衰退は止まらないと。 読了日:5月2日 著者:チャールズ・ファーガソン,CharlesFerguson  記者たちは海に向かった 津波と放射能と福島民友新聞 (ノンフィクション単行本)の感想 記者たちは海に向かった 津波と放射能と福島民友新聞 (ノンフィクション単行本)の感想故郷の過酷な惨状、自身と家族と同郷人の消えかかる命、たたみかける放射能汚染、これらの御しきれない状況の中で、報道人として郷土新聞として使命を果たそうとする人々の格闘の記録に悲しみがこみ上げます。「運命」としてなんとか前を向こうとする人、悩み続けて背負って生きる覚悟をする人、一生を捧げる決意をする人、その姿は尊く強く孤高に思います。悲劇と再生への誓いの記録です。 読了日:4月26日 著者:門田隆将  黒澤明が選んだ100本の映画 (文春新書)の感想 黒澤明が選んだ100本の映画 (文春新書)の感想30作くらい観た作品がありましたが、知らないものも多く、紹介されているものを観るのが楽しみです。黒澤監督は、野太い人間ドラマのイメージが強いのですが、紹介されている映画は様々な価値観のものがならんでいて、自身の作風とは違った様々なジャンルのものを好まれていたのに驚きました。アニメ、カーチェイスものまであるとは。創造の才には敷板など存在しないのですね。 読了日:4月26日 著者:黒澤和子  倒れゆく巨象――IBMはなぜ凋落したのかの感想 倒れゆく巨象――IBMはなぜ凋落したのかの感想モラールの高い従業員の先進的文化を有した最新技術に邁進する高品質企業と思ってましたが、実は、コスト削減での決算作り、大量解雇、非正規雇用、安い労務費を求めた国外移転、国内残業規制・過重勤務、収益優先、顧客軽視、品質軽視、SLA軽視、係争決着、株価重視、借金して自社株買い一株あたり利益捻出と、浮利を追う会社に変貌していたとは著者の指摘に驚ぎます。本当であるとするとまさにブラック企業です。品質問題でディズニー、ヒルトン、テキサス州など取引止めたらしいです。著者は破綻すると断言してますがどうなんでしょうか・・・ 読了日:4月24日 著者:ロバート・クリンジリー  世界を操る支配者の正体の感想 世界を操る支配者の正体の感想長谷川慶太郎は競争力のないロシア製品を売る国としてウクライナをロシア依存にしておきたいからと。佐藤優と池上彰は、歴史的にクリミアはロシアが庇護し、フルシチョフはウクライナを思いクリミアを併合させたと、ウクライナとは田舎との意味。本書はEUもドイツもウクライナの取り込みには長年難色、米独のウクライナ援助も自国企業の債務保証で自国の為。真の人道支援は水道支援の日本のみ。紛争の真相はプーチンを煽り軍事行動させて抹殺しようとする米と国際金融勢力の陰謀と。ユダヤ勢力、グローバル化の真実と驚く内容。さてどうなのか・・ 読了日:4月22日 著者:馬渕睦夫  もう一度 天気待ちの感想 もう一度 天気待ちの感想爽快で痛快で力が湧いてくるのが黒澤映画なのですが、この本の製作の裏話の数々もなんだか映画と同じように気持ちの良いものでした。苦労も喧嘩も前向きな必要なものに感じられ、反目も離反も次元が高くて理解しあい尊重しあう人間にとっては好ましい必然な事で、彼らにとっては存分に生きている幸せの証のように思えてきます。しばらくぶりにまた黒澤映画を観たくなりました。「あばよ」や「裏切り御免」との捨て台詞のシーンなのに、とても爽快な別れのシーンが忘れられません。すみずみまで躍動する迫力満点の白黒画面をまた観たくなりました。 読了日:4月20日 著者:野上照代  沈みゆく大国アメリカ (集英社新書)の感想 沈みゆく大国アメリカ (集英社新書)の感想チャールズ・ファーガソン強欲の帝国、ジョージ・パッカー綻びゆくアメリカのなぞりの印象。両書での「アメリカが林冠経済で出来レースの国で二大政党とは複占政治体制で金融と寡占企業と富裕層に魂を売り渡してる」「毎日低価格で過ごしてるが、不平等が広がり続けて抜け出せず、正義は金持ちの為でメディアも信頼できない」を再確認。オバマは貧困ビジネスモデルを医療保険制度改革に導入して寡占の医療保険会社、製薬会社、ウォール街につくすと。日本も狙われてると。週刊誌的で読み易い分、肝心の制度や財務がわからない本でした。煽り? 読了日:4月19日 著者:堤未果  明治維新と幕臣 - 「ノンキャリア」の底力 (中公新書)の感想 明治維新と幕臣 - 「ノンキャリア」の底力 (中公新書)の感想明治維新で全国統治の行政能力と行政官を持たぬ新政府が、幕府の行政組織と要員を継続登用してのりきったという主題でとてもおもしろかった。下級武士、外様の大名達の革命的歴史ドラマとして馴染んだ明治維新ですが、行政面で明治を支えたのが幕臣であったとは新鮮な視点でした。江戸の町奉行所も箱館奉行所も実務者たちがそのまま明治の初動を支えたとは。更に近代化が進み始めると彼らは去り、旧旗本の資産家階級出身者が優秀なキャリアとして復権したそうで、なんだか今でもあるような話の印象。福沢諭吉の痩せ我慢の説、よくわかりました。 読了日:4月17日 著者:門松秀樹  黒幕: 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」の感想 黒幕: 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」の感想バブルとその後に繰り広げられた政・官・財・暴の詐欺、横領、汚職、粉飾、破廉恥、破綻、逮捕、投獄の総ざらいで、欲望に狂奔していた世相を思い出してあの頃の日本社会への嫌な思いがよみがえってきました。本書の情報誌主宰者は、表と裏をつなぎ、先手の情報戦を指南して事を治めてきた人物のようで、窺い知れない複雑で繊細で肝の据わった生き様であったようですが、正義を笠に着るような右や左の権勢の嘘を見抜き、右でも左でも、商売でも公務でも、表でも裏でも、それぞれの分野でまっとうであることを求めていた人物であるような印象でした。 読了日:4月14日 著者:伊藤博敏  奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家・木村秋則の記録の感想 奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家・木村秋則の記録の感想大規模農業に邁進していた探求心の強い人が一冊の本との出会いで新しい農業の在り方に挑み、信念に全てを捧げ、家族もその信念を信じて支えるも、困窮、赤貧、孤立の末に、一人命を捨てに岩木山中に入り、自然の中で実をつける木を見て自然の土、生態系の力を悟り、更に探求を重ね、新しい農業を実現した一生。感動しました。貧困に負けぬ信念と取り囲む人々の自然な態度と到達した境地に心が震えます。賛同が広がる日本の農業に未来の期待が膨らみました。 読了日:4月10日 著者:石川拓治  日本の風俗嬢 (新潮新書 581)の感想 日本の風俗嬢 (新潮新書 581)の感想今村昌平監督の女衒や、山崎朋子のサンダカン八番娼館などで、戦前までの貧困から身をやつさざるをえなかった女性たちの痛々しくも逞しく耐え抜いた話にふれ、圧倒されて何も言えない思いをしたことがありましたが、一世紀をへだてた日本でも、貧困から足を踏み入れることになる人が多いとは驚くばかりです。一方、割り切り持てる力を使い高収入を得る職業人層もいて、二極化した格差社会の縮図がここにも拡がっているとは・・・存在する事実として社会からはじくのではなく、現実的支援や規制が必要との著者の主張に頷くばかりです。 読了日:4月9日 著者:中村淳彦  日本財政「最後の選択」の感想 日本財政「最後の選択」の感想アベノミクスが登場した財政の背景、経済対策の緊急度、消費税アップとその延期の意味に納得。借金漬けの中で、逃げられない人口動態の未来にどう政策対応するか、様々なシナリオの検証結果をみせられ背筋が寒くなります。消費税率を15%まで引き上げ、かつ成長率を引き上げないと2020年代には国債残高が国債購入に回る家計と企業の貯蓄を上回り債務危機に陥る可能性が高いと。政治に課せられた責任の重大さに果たして彼らでかじ取りしきれるのか不安倍増です。2015年から二年で何を実行するかが最後の選択とは・・・ 読了日:4月7日 著者:伊藤隆敏  張り込み日記の感想 張り込み日記の感想黒澤明の映画を見ているような気がしました。構成乙一が頷けます。下町風景ですが、広々と小綺麗な印象を受けました。映画のような躍動が溢れる写真集でフランスで刊行されたのもうなずけます。刑事捜査を実写できた時代にもおどろきます。 読了日:4月5日 著者:渡部雄吉,構成と文乙一  日本‐喪失と再起の物語:黒船、敗戦、そして3・11 (下)の感想 日本‐喪失と再起の物語:黒船、敗戦、そして3・11 (下)の感想少子高齢化で縮退する経済、閉塞状態の若者と未来の活路を探す若者の併存、男性社会と女性差別と女性活用と晩婚化と女性保守化が混在した男女関係、左派講座派的に歴史批判、安倍一次総理と鳩山とも日本を普通の国にしようとして惨敗、日本の国民は平和憲法を支持、第二次大戦の資源確保の必要性についてはナチスの考え方に酷似、原発事故で官僚と政治家の無能を露呈、日本人は政官財すべてに不信感、日本は市民社会として発育不全・未熟、震災で改善兆し、震災復興に人々は懸命とのことでした。引用が多い手法で新聞記事からも多く注意しました。 読了日:4月5日 著者:デイヴィッドピリング  あんなに大きかったホッケがなぜこんなに小さくなったのか (単行本)の感想 あんなに大きかったホッケがなぜこんなに小さくなったのか (単行本)の感想大変いい本でした。魚好きはもはや心して考えなければならないのですね。ご都合主義の水産庁、取材せずお上の発表垂れ流しマスコミを鵜呑みにせず、自分で考えてくれとの著者のメッセージは悲痛です。魚の資源破壊は、行政、政治の失敗で、更に根底に「乱獲、乱売、乱食の負のスパイラル」があるのもよくわかりました。和食は遺産でなく遺物になってしまうのかと心配になりました。でも福島沖がこの三年で豊かな魚の海に戻ったとは驚きました。海と魚の回復力はすごいのですね。汚して根絶やしにしてしまうのは人間で浅ましいかぎりです。 読了日:3月31日 著者:生田與克  プリズム (幻冬舎文庫)の感想 プリズム (幻冬舎文庫)の感想作者の人間賛歌が好きですが、今回は主題を掴みきれませんでした。 読了日:3月29日 著者:百田尚樹  ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由の感想 ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由の感想今年、英国ウイリアム王子が郡山に一泊したのは要人初で、震災直後25か国の大使館が東京から避難した時、英仏伊は留まり、英国大使館は二日後には車を連ねて仙台入りし、3日間避難所を回り、支援物資配布と英国人安否確認をしたとの記事を読みました。ドイツは本国からの指示で3月18日大阪の総領事館に避難し、その時の大使が著者だそうで、それをドイツ人からも非難され、奥さんからは一番怒られたそうです。一か月後、東京に戻り、集会を開いて話し合い、政府の立場を説明し、被災地に何ができるか話し合い、支援がはじまったそうです。 読了日:3月29日 著者:フォルカー・シュタンツェル  イギリス、日本、フランス、アメリカ、全部住んでみた私の結論。日本が一番暮らしやすい国でした。 (リンダブックス)の感想 イギリス、日本、フランス、アメリカ、全部住んでみた私の結論。日本が一番暮らしやすい国でした。 (リンダブックス)の感想米英仏の典型的な働きぶり、生活ぶり、育児ぶりがよくわかり、楽しめました。仕事、教育、格差、差別など米英仏の体感実態が伝わってきて面白く読めました。さて、どこが一番幸せに感じている人が多いのか、何処もそれぞれに自国がと言う国民性ではないかという気がします。日本の自己満足刺激をネタにする番組が多いですが、そうではない米英仏日よく比較できていて納得感ありました。 読了日:3月28日 著者:オティエ由美子  餃子の王将社長射殺事件の感想 餃子の王将社長射殺事件の感想闇社会がつくづく恐くなりました。企業の脇固めの難しさ、トラブルへの安易な対応の怖さ、忍び寄る執念深い魔の手、痕跡を残さぬ狡猾な手口、弱みを持つことの危険さ、闇社会の海外進出、闇社会の国内流入、企業の成長につきまとう暗部などなど驚くばかりです。このような事が起きている日本でも安全との評価が得られるとなると、海外はよほど危険極まりないことになります。反社がすでにアジアに進出してて日本人や日系企業を狙っているとはおそろしい限りです。 読了日:3月22日 著者:一橋文哉  日本‐喪失と再起の物語:黒船、敗戦、そして3・11 (上)の感想 日本‐喪失と再起の物語:黒船、敗戦、そして3・11 (上)の感想日本の近現代史を各種書物、報道、口伝などをまとめたもので、週刊誌的で読み易く面白かったです。歴史を良く勉強されたようで様々な人の見解が引用されています。但し、引用された内容が異論と比較吟味できてるか、部分引用の切り出しが適切か注意が必要でした。本人への取材もありましたが、心象記述もあり、実証的歴史というより、随筆的印象でした。 読了日:3月21日 著者:デイヴィッドピリング  新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方 (文春新書)の感想 新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方 (文春新書)の感想世界の紛争の背景、論理、行末がわかりました。それにしても過去の帝国主義国、共産主義国の所業の悪辣さには、恐れ入ります。民族の領土覇権が入れ代わり立ち代わりの収奪の応酬を招き、人々を猜疑的に敵対的にしてゆく歴史が悲惨です。宗教と民族を抑圧でなく調和する文明がないものかと思います。豊かさを分かち合う文明はもうありえないのでしょうか。偽善的、潜脱的な拝金主義が著者の一人が言う「新帝国主義」の正体かと思います。米国でも差別にあえぐ若者が神の前に皆平等とするイスラムになびいてしまうことがあるとの指摘に怖くなります。 読了日:3月17日 著者:池上彰,佐藤優  絶対に行けない世界の非公開区域99 ガザの地下トンネルから女王の寝室までの感想 絶対に行けない世界の非公開区域99 ガザの地下トンネルから女王の寝室までの感想秘蔵写真を期待しましたが、各地でのいわくつきの場所についての読み物でした。知らない世界をのぞくような面白さはありましたが、米国本土の施設関係が3割を占め、他国でも米軍の関係する施設が紹介されてます。殺伐とした軍事・情報・金庫・刑務所などの各地の閉ざされた風景が多く、清々しく憩えたのは、伊勢神宮でした。 読了日:3月13日 著者:ダニエル・スミス  ドクター・ハック: 日本の運命を二度にぎった男の感想 ドクター・ハック: 日本の運命を二度にぎった男の感想とても面白い歴史です。ドイツ人武器商社員が、ヒトラー直属の諜報組織員で駐独日本陸軍の依頼で日独防共協定の日本での根回しをし、成果をあげたもののヒトラーの正体を見抜き反ナチに転じ逮捕されるも、駐独日本海軍武官が救いだし、スイスに亡命。開戦後は日本の武官に情報支援し、終戦に向けてOSSのダレス機関と日本の海軍武官達の終戦工作を斡旋。吉村昭の深海の使者での絶望的試練の先に、日本の破綻を救おうと信義にもとづくスパイ活動があったとは。軍国主義に虐げられる時代に親愛された日本人もいたことがわかります。 読了日:3月11日 著者:中田整一  日本の古代道路 道路は社会をどう変えたのか (角川選書)の感想 日本の古代道路 道路は社会をどう変えたのか (角川選書)の感想7世紀末から2百数十年間に亘る古代の国道のお話で、延6300km、直線、幅6〜10m、16km間隔に駅、駅は宿泊可、規程数の馬と要員常備だったそうで、奈良、平安時代の律令国家の実力には驚きます。人、物、米、文明の流通・伝播・軍事効果は大きく、制度が廃れた後も道としての効能は計り知れないと。但し、制度維持した農民の苦しみは避けられず、政治的、経済的余波も大きかったそうです。佐藤健太郎氏の「ふしぎな国道」も面白かったですが、本書は国道の原型でした。古代人のダイナミックな活動実態がわかりとても面白かったです。 読了日:3月7日 著者:近江俊秀  ニッポンの裁判 (講談社現代新書)の感想 ニッポンの裁判 (講談社現代新書)の感想冤罪事件がなくならず、今でも起こされている。なぜなのかよくわかりました。まさか、最高裁判所や特捜検察が、「組織の維持と権益確保が自己目的化」した「腐敗した組織」とは・・・ その検察のリークを正義と報道する迎合メディアしかないとは・・・ 「日本の司法が中世並み」であるとは・・・ 裁判官が劣化し、訴訟当事者からの提出書面のコピペで判決を作成しているとは・・・ 権威主義、事大主義、大勢追随の裁判官ばかりとは・・・ 最高裁が憲法の番人ではなく、権力者の番人になり下がっていたとは・・・ やはりそうだったのか・・・ 読了日:3月4日 著者:瀬木比呂志  日本人に生まれて、まあよかった (新潮新書)の感想 日本人に生まれて、まあよかった (新潮新書)の感想近現代史の正しい理解の仕方がよくわかりました。メディアに違和感を感じる事が多いですが、それは誤っておらず、むしろ、今も昔も日本のメディアが簡単に堕落したことをするのがよくわかりました。明治の修養・開明、大正・戦前の自己満足・懈怠、戦後の扇動・盲信がよくわかりました。リベラルとは何か合点できます。結果平等という偽善と、競争原理の排除が教育に弊害をきたし、日本は二流国家になるとの著者の危惧は迫真です。日本の左翼が日本にもたらし続けている被害にも呆れます。とりわけ朝日新聞の罪の深いこと、深いこと、救われません。 読了日:2月28日 著者:平川祐弘  インスタントラーメンが海を渡った日: 日韓・麺に賭けた男たちの挑戦の感想 インスタントラーメンが海を渡った日: 日韓・麺に賭けた男たちの挑戦の感想二国間でいい話のひとつでもないかと期待して読んでみましたが、如何せん、構成、文脈が未整理で正直読みづらい著作でした。明星食品の奥井清澄氏と三養食品の全仲潤氏について興味は湧きましたので最後まで読み通しましたが、途中、話が著者の随筆めいたり、小説めいたりします。登場人物の会話で表現してるのですが、主語、脈絡が曖昧で、果たして著者の取材によるものか、フィクションなのかと迷うことが間々ありました。韓国民は植民地支配を忘れず、許さず、謝罪を求めるとの主張も入ってます。題材はよさそうなのに残念な気がした著作でした。 読了日:2月23日 著者:村山俊夫  羆嵐 (新潮文庫)の感想 羆嵐 (新潮文庫)の感想マーチン・スコセッシは、今村昌平監督の古い映画を見つけると新作を見出したように嬉しいとの談話をテレビで見たことがありますが、吉村昭の作品にも調度そのような気持ちになります。未読の作品は楽しみで、かえって手に取るのをためらうことがあります。本作も今日読んでしまいました。張りつめた凍てつく世界に、開拓民の温もりが消えいるようで極限の営みにひとしおの寂寥感が漂う作品でした。日本人の自然環境との格闘には、獣との命のやりとりもあったことに驚きます。毎度のことですが、読後にはふうーと一息ついて心を落ち着かせます。 読了日:2月20日 著者:吉村昭  中国の大問題 (PHP新書)の感想 中国の大問題 (PHP新書)の感想14億人もの巨大な国のかじ取りのすさまじさがよくわかりました。内に抱える地方と都市の戸籍による大格差、都市への大流入と底辺生活、1億人以上に達する少数民族、日本と相似の成長軌跡、内需による発展段階突入、インフラ巨大投資の内需拡大継続、独仏韓新興国の果敢な進出、バブルはじけても巨大経済は崩壊なし、国営企業は非効率、人口は年6百万以上増加中、教育関係予算は国防予算の三倍、科学技術の研究者数は米より多い、留学は年20万人で帰国後優遇措置。次世代への布石着実。本書の主題は、日本は大問題、たちすくみ、能天気でした。 読了日:2月17日 著者:丹羽宇一郎  現代の正体 深夜の書斎から日本を思い世界に及ぶの感想 現代の正体 深夜の書斎から日本を思い世界に及ぶの感想著者の現代社会を知りたいとの読書を通じての思索の紹介でした。現代社会の正体が暴露されているものではなく、著者が現代社会の正体を知るために重ねた読書と触発された思考の紹介本でした。 日本は西洋的近代化に成功した最初の非白人国で西洋的近代に相当程度共感することができるが、西洋の植民地となり、勝手に国境線を引かれた人々は西洋的近代化に日本人のように権威を認めず、尊敬心を抱いていないだろうと。イスラム、ヒンズー、共産しかり、核心かと思います。日本は、いずれも解せる国と自覚して行動すればもっとよくなると思いました。 読了日:2月15日 著者:牛島信  天、共に在りの感想 天、共に在りの感想素晴らしい本でした。著者の自然で誠実で賢明で利他的な事績に圧倒されます。このような方がおられて、とても嬉しいです。戦争、貧困、平和、民族、生活、繁栄、文明、貢献といった事の本質が何なのか深く考えさせられます。大切にすべきものとは何なのか、考え抜き、やりおおせるとはどういうことなのか考えさせられます。したり顔の評論も愛国的な政治も真実面のマスコミも吹っ飛びます。日本の人々へと題された終章はこの上ない説諭でした。 読了日:2月12日 著者:中村哲  桜色の魂~チャスラフスカはなぜ日本人を50年も愛したのかの感想 桜色の魂~チャスラフスカはなぜ日本人を50年も愛したのかの感想波瀾万丈の人生に圧倒されました。最高水準の演技者同志の以心伝心の意気、スポーツと武士道の相似性、共産主義の人権抑圧とその全体主義的本質と残虐性、抵抗する人の矜持、日本体操陣の高貴で忍耐強く優しい人間性など、20世紀後半の歴史を象徴する実録ドラマでした。今、日本人としてどうなのか、考えさせられます。 読了日:2月9日 著者:長田渚左  狼の牙を折れ: 史上最大の爆破テロに挑んだ警視庁公安部の感想 狼の牙を折れ: 史上最大の爆破テロに挑んだ警視庁公安部の感想団塊の世代が青春時代に起こした暴挙と、それを糺した正義の実録でつくづく平和な今を有難く思います。共産主義、社会主義の熱に浮かれ身勝手にも無防備の人々の生命を奪った行為が横行した時代であったこと、卑怯な若者が爆弾テロを行っていたことを思い出して悲しくなりますが、同世代の恵まれない境遇の若者が彼らを許さず捕えたことも知り感動しました。本書の巻末の年表にある団塊世代が起こした陰惨な事件の数々は、拭いきれない戦後の汚点とつくづく思いました。 読了日:2月8日 著者:門田隆将  税金を払わない巨大企業 (文春新書)の感想 税金を払わない巨大企業 (文春新書)の感想注意して読む必要があった。持ち株会社制度批判であるとすると何が誤りなのかよくわからなかった。 読了日:2月5日 著者:富岡幸雄  綻(ほころ)びゆくアメリカ―歴史の転換点に生きる人々の物語の感想 綻(ほころ)びゆくアメリカ―歴史の転換点に生きる人々の物語の感想アメリカの様々な人々の今がよくわかりました。二大政党とも金融界に染まっていること、金への野心に知識人は邁進していること、尊敬され魅力ある英雄が初の黒人大統領にはならなかったこと、開発業者と銀行と行政とが主犯の住宅ローン詐欺がリーマンショックであること、正義を求めて闘い続ける人もいること、格差は食生活に及ぶこと(豊かな食文化を楽しむ富裕層とジャンクフードに追い込まれる人々)、財務長官歴任者でも人格は強欲であることなどなど。驚きました。科学者以外、各分野総ざらいされてます。 読了日:2月4日 著者:ジョージ・パッカー  化学で「透明人間」になれますか? 人類の夢をかなえる最新研究15 (光文社新書)の感想 化学で「透明人間」になれますか? 人類の夢をかなえる最新研究15 (光文社新書)の感想著者の「ふしぎな国道」は、軽妙でリズムのよい奇妙なネタで面白かったので、本書も読んでみました。化学の苦手が少し癒された気ができまして、化学の仕組み、その有用性と限界が面白いです。金、ダイヤモンド、カーボン、薬の数々から温暖化、エネルギーまで、取り組む人々が生き生き感じられました。楽しい読み物です。 読了日:1月29日 著者:佐藤健太郎  大格差:機械の知能は仕事と所得をどう変えるかの感想 大格差:機械の知能は仕事と所得をどう変えるかの感想原題は、Average is over。アメリカは、富豪が15%に増え、所得が頭打ちか減少するかする人が85%になると。機械の知能を使える真面目な労働者が求められ、そうでない人は技能の要らぬ低賃金労働しかなくなると。やる気があって勉強し続けて、賢い機械と協働できないと成功しないと。今のアメリカは雇いたくない人が多くて、教育長官曰く、17才から24才の人で4人に3人は軍入隊不適格者(麻薬、借金、肥満など)と。格差は拡大しても北米の世紀になると。低賃金労働力頼みの中国はそのままでは行き詰ると。日本はまだまし? 読了日:1月24日 著者:タイラー・コーエン  夕張再生市長 課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒントの感想 夕張再生市長 課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒントの感想マスコミで見聞きはしていましたが、事の本質が始めてよくわかりました。格闘し、勉強し、考え抜き、話し合った末に、立派な青年政治家になられたことがよくわかりました。民主主義の原点に忠実な心ふるえる政治活動に感動しました。打ちひしがれた夕張の人たちが立ち上がりはじめたことは貴いことです。成功を祈るばかりです。 読了日:1月20日 著者:鈴木直道  フォルトゥナの瞳の感想 フォルトゥナの瞳の感想フォルトゥナとは、作中の説明では、「ローマ神話に出てくる球に乗った運命の女神。人間の運命がみえる。」だそうです。面白い話でしたが、「類、種、個」の種の少ない話でした。 しかし、多崎つくるとは違う世界を見せてもらいました。ゼロや海賊とは異次元で"巡礼・・"に近いかもしれませんが、根底の人間大好きな気持ちが溢れてました。 読了日:1月19日 著者:百田尚樹  大局を読むための世界の近現代史 (SB新書)の感想 大局を読むための世界の近現代史 (SB新書)の感想著者の『大破局の「反日」アジア、大繁栄の「親日」アジア』も明快でしたが、本書もわかり易く納得させられました。30年前にソビエト軍の一線の兵士と武器の実態から国家としての危うさを予言した眼力は、もう80才をとうにすぎておられますが、いまだ衰えずと感心しました。人民解放軍、中国経済、中国共産党を正しく理解できた気がします。遅かれ早かれ北朝鮮が中国に見捨てられて崩壊し、その後2年で中国が崩壊するとの予言は、迫真です。そして、日本は、中韓に巻き込まれず静観せよ、連邦国家、民主国家になるまで待てとの警告も得心です。 読了日:1月18日 著者:長谷川慶太郎  しんがり 山一證券 最後の12人の感想 しんがり 山一證券 最後の12人の感想1997年11月に大蔵省から見限られ自主廃業となった山一証券の翌年4月に社内調査報告書を公表して不正を検証した事績が明かされる。マスコミは全く本質を掴んでおらず、会社を大切にした傍流の社員が真実を掴み、私利私欲の歴代社長とその取り巻きを弾劾したノンフィクション。強欲の行き着く果ての破綻話の後日談となるが、志ある正義にすくわれる爽やかな物語。アメリカの「強欲の帝国」や「綻び行くアメリカ」のような救いようのない閉塞話とは一味違う、強欲な金融悪に憤る人間賛歌でした。 読了日:1月15日 著者:清武英利  殺人犯はそこにいる: 隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件の感想 殺人犯はそこにいる: 隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件の感想以前、文芸春秋や報道番組で見聞きしていましたが、改めて全体を読み、警察、検察、裁判所、報道機関の深い闇に驚愕しました。痛々しい被害者の救済、犯人の検挙よりも、自己の組織を守ることを優先する権力構造に堕落の極みをみるようです。著者の職業倫理と正義感には感服します。ノンフィクションの真髄のような本でした。 読了日:1月11日 著者:清水潔  米軍と人民解放軍 米国防総省の対中戦略 (講談社現代新書)の感想 米軍と人民解放軍 米国防総省の対中戦略 (講談社現代新書)の感想否応なく突きつけられている軍事情勢がよく解りました。自国の利益を最終的には優先して自国の利益至上で邁進する同じような価値観のアメリカと中国。そして対峙しているアメリカ軍と中国軍。その攻撃的な武器の準備状況がよくわかりました。その膨大さは、恐ろしいものです。論理的で戦術的な分析・解説がなされるほど、目的と手段の逆転、自己陶酔型の試みを感じてしまいます。著者は、米軍関係者に開戦の分析はあるが、終戦の検討が欠けていると、中国軍の最高位の委員会では、文民は習近平ひとりで、他は皆、軍人と。暴発しないとよいですが。 読了日:1月10日 著者:布施哲  深海の使者 (文春文庫)の感想 深海の使者 (文春文庫)の感想昭和17年から20年までに繰り広げられたドイツの最新兵器の技術情報入手ための潜水艦による輸送記録に圧倒されます。100メートルを超え、100人規模の乗員を要する伊号潜水艦、小ぶりながらすぐれた建造技術と最新レーダーを備えたUボート、果敢に実用化された長距離飛行機の活動記録と悲劇が丁寧に披露されます。 それらを駆使してシンガポールからヨーロッパまでの喜望峰を回る大航海の隠密行動に果敢に挑み、絶命していった優秀な技術者や軍人に悲しみがこみ上げます。 読了日:1月4日 著者:吉村昭 読書メーター |