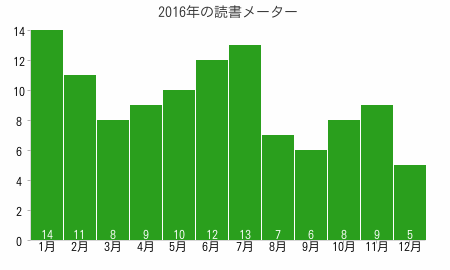
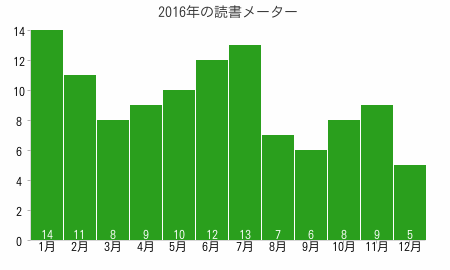
|
2016年の読書メーター 読んだ本の数:112冊 読んだページ数:31794ページ ナイス数:1365ナイス  日本人になりたいヨーロッパ人 ~ヨーロッパ27カ国から見た日本人~ (宝島SUGOI文庫)の感想 日本人になりたいヨーロッパ人 ~ヨーロッパ27カ国から見た日本人~ (宝島SUGOI文庫)の感想自己陶酔、自己憐憫の裏返しのような娯楽放送やネット動画が増えているが、そのネタ本かと注意読書。ヨーロッパと日本の間の肯定的話題の総ざらいで、偏面であるかもしれないが、話材として楽しめた。日露戦争勝利でトーゴービール登場の話は、怪しい話で、あるにはあったが実状は別らしい。天声人語のトーゴービールの記事が紹介されており、また、裏取りなしで談話形式で責任逃れした記述の可能性が見えた。出島の独人医師ケンペルによる綱吉施政評価の紹介があり、現代での新しい解釈と同じで面白い。日本を安心したい気分の時に丁度よい本。 読了日:12月31日 著者:  偽りの帝国 緊急報告・フォルクスワーゲン排ガス不正の闇の感想 偽りの帝国 緊急報告・フォルクスワーゲン排ガス不正の闇の感想真相がよくわかった。三菱自動車と似たような、組織に属する人間達の保身の病根が、権威主義の経営者により発病していく構図で、企業が腐る典型だ。エンジニアとして一流の人々が目標を与えられて、上意下達の服従に保身しながら、目標に邁進して、見せかけの実現を遂げていったらしい。油を注いだ背後にドイツ人の米国を見下す本音があったり、企業体質が、創家、ヒトラー、占領英軍の影響によるものだったりとは驚き。それにしても今年、宿願の世界一をとるとは皮肉なものだ。 読了日:12月31日 著者:  最悪の将軍の感想 最悪の将軍の感想綱吉と正室の心に沁みる風雅な夫婦物語でもあった。恋歌もそうだが、武家の出でない妻の視線が実は武家らしい。清水克行によると、近年、綱吉は都市の治安と人心の教化に成功したとの評と。悪評の生類憐みの令は、実は、戦国気風ぶった愚連隊対策と、農村での銃規制に狙いがあったとも。作中に綱吉の政治の評価は百年かかるかもとのセリフがあるが、三百年かかったことになるのか。作中、綱吉に穢れ扱いされる忠臣蔵は、堺屋太一によると、もともと稀有のできごとで、実は不義不忠が普通の時代だったと。実は、この本が真実かも。 読了日:12月28日 著者:朝井まかて  アメリカ・ザ・ゲンバ - America at the Scenes - (ワニブックスPLUS新書)の感想 アメリカ・ザ・ゲンバ - America at the Scenes - (ワニブックスPLUS新書)の感想13年前のイラク戦争侵攻直前の本の改題本だが、現場ネタは実に読みごたえがある。米の傲慢と公正と強欲が共存して世界に君臨してきた理由がよくわかる。対等な者同士にしか公正に接せず、認めない相手には不公正に接することも米欧にとっては、公正であるとの傲慢思想には呆れるが、さもありなん。マスコミ、映画の堕落と、その垂れ流しを喜んで過ごす日本人。そうだろう。そんな日本人の未来を支えるのは、仕事のでき・質に拘りぬく世界で唯一の至上の存在であることだと。果たして大丈夫なものなのか。 読了日:12月17日 著者:青山繁晴  「カエルの楽園」が地獄と化す日の感想 「カエルの楽園」が地獄と化す日の感想中国が日本を侵略したい切羽詰まった動機には驚く。まさかと思いつつもスターリン、毛沢東の自派以外や他民族への粛清殺戮暗黒史を考えれば、そうかもしれないとも思う。長谷川慶太郎は、中国共産党の独裁支配の崩壊は間違いないと言うが、一方で日本自身が瓦解してしまうと話は別だ。つまり、反日新聞社・テレビ、左巻き評論家・学者・教師・自称市民活動家など左翼ネタの商売人達が、中国工作員達に煽られ、在日米軍、自衛隊を貶め、日本人は戦わぬ衆に馴らされ、お人よしにも、凌辱者を受け入れて瓦解してしまう可能性だ。果たしてどっちが先か。 読了日:12月7日 著者:百田尚樹,石平  挽歌の宛先 祈りと震災の感想 挽歌の宛先 祈りと震災の感想真実に迫ったドキュメントだった。祈りは、悲しみと向き合うことで、亡き人を想い同時に生き残った者同士の励ましでもあるそうだ。河北新報社ならではの取材で、人の真相に迫る報道だと思う。生きることを報道できる数少ない立派な新聞社なのだろう。「寺院消滅」「無葬社会」の淵なしの闇の答えがここにある気がした。多死社会を迎え、限られた時間に対してどのような平安を用意できるか、送る者に問われていると気づかされた。 読了日:11月30日 著者:河北新報社編集局編  魚影の群れ (ちくま文庫)の感想 魚影の群れ (ちくま文庫)の感想仕事して生活する営みが、動物、海、四季との格闘でもあったことを思い知らされる話だった。いつもながら、繰り広げられる人々の人生は、地道でも波瀾にまみれ、なんとか冷徹な現実に折り合いをつけるものだった。現在の規律ある社会でも、人々の底には、本能的に捨てがたい渇望があることを描いていると思う。捨てられぬ生き方、捨てたときに救われる現実、やめられぬ性向、奪う者への憎悪、愛情と嗜虐の同居など、4編とも息づまる迫力だった。 読了日:11月27日 著者:吉村昭  アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄 (祥伝社新書)の感想 アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄 (祥伝社新書)の感想トランプが勝った事に得心。アメリカも左巻きメディア、既得権益死守強奪エリート層の政権たらいまわしにうんざりした拒絶意志表明のようだ。左巻きと利権漁りエリートが組み合わさっている中央政府という事らしい。それが、1930年代からとは。コミンテルンとはそれほどに賢く抑制の効いた策謀勢力だったのか。ヴェノナ文書なるNSAとFBIの40年前の文書公開での歴代共産主義スパイ暴露は読んでみたい。長谷川熙の「崩壊朝日新聞」での日米開戦を扇動した朝日左翼秘密結社説が、アメリカでは大統領府で起きてたと。ハテ白黒つくか。 読了日:11月26日 著者:江崎道朗  冬の鷹 (新潮文庫)の感想 冬の鷹 (新潮文庫)の感想題名の由来に思いがはせる。作中、鷹らしい下りは、田沼意次の失脚のキッカケが将軍鷹狩時の田沼手配の同行医師の治療のところか、前野良沢と晩年親交した尊王攘夷志士彦九郎にイワナを下賜した上杉鷹山の名前くらいだった気がする。良沢が孤高で群れぬ探求者であることを「鷹」にこめ、雪に埋もれる根岸の清貧の小屋から嫁いだ娘に助け出される老境を「冬」に表しているのかも。拝金功利流行医と対比した、偉業を成した探求者の姿を冬の鷹としたのか。対比は現代社会の性根暴露にも見えた。実に面白い。 読了日:11月23日 著者:吉村昭  ハーバードでいちばん人気の国・日本 (PHP新書)の感想 ハーバードでいちばん人気の国・日本 (PHP新書)の感想流行りの自己満足受け狙いかと注意読書。近頃のハーバードの学生はエリート富裕層の子弟で小粒の人間が多いとの記事を以前読んだが、勝者教育は続いているようだ。基本は勝利指向の選民教育に変わりはないのかも。和の思考・倫理もそのための方法であれば、思考材料として学んでいるようで人間教育とはちがう印象。同大のテキストのコピぺ本で、通説が多く、内容は、日本の商業新聞と同じ印象。「強欲の帝国」を支えるつるんだエスタブリッシュ養成教育での息抜きが日本のケース学習か、勝者教育の反面教材が本音か。知日と親日は別。おめでたい。 読了日:11月19日 著者:佐藤智恵  氷の燃える国ニッポン (ワニブックスPLUS新書)の感想 氷の燃える国ニッポン (ワニブックスPLUS新書)の感想海洋資源分野も、新聞、テレビ、中央官庁、学閥、エネルギー独占企業に食い物にされ、事実を葬られているとは。既得権益にたかる学者、研究機関、中央官庁、いずれもが、保身のために権謀の限りを陰湿に繰り出し、日本の未来を摘んでいるとは。予算の獲得と費消に腐心し、時間稼ぎで成果を先送りするとは。まだこんなことを。エリート政官民の腐ったもたれ合いのたかりが横行してるとは。日本海沿岸自治体が連合せざるをえないわけだ。自前の資源で賄える国になる可能性が、敗戦洗脳による利権確保勢力にまたも攻撃されるとは。やるせない。 読了日:11月17日 著者:青山千春,青山繁晴  無葬社会 彷徨う遺体 変わる仏教の感想 無葬社会 彷徨う遺体 変わる仏教の感想増田寛也の地方消滅と、松谷明彦の東京劣化の構図が、前作の寺院消滅と、本作の構図と重なった。近代文明が経験していない高齢社会と多死社会の到来がどのような姿、形となって迫ってくるのかが少し見えてくるような現代世相ルポだった。日本の寺には律がなく、世俗化してしまっていて、本来の布施で生きて、修行する姿を挺して社会に貢献するアジアの僧とは全く異なるらしい。救いの場とならない僧が私有化している寺は、税金払うべきとの佐々木閑の話は納得。多死無縁社会では弔いや葬送の文化は手続きに変容するようだ。 読了日:11月15日 著者:鵜飼秀徳  これが世界と日本経済の真実だの感想 これが世界と日本経済の真実だの感想新聞社とテレビが既得権益に守られ、安逸をむさぼれるのがよくわかった。株式譲渡制限、再販制度、国有地安価な払下げで守られ、教条的な非論理の不勉強な安易な報道ですむ気楽な権益商売とは。マスコミが嘘八百になるはずだ。郵政民営化は郵貯の破綻を民営化で回避するためで、年一兆円の人件費税金補てんをしていたので存続できていたとは。国債に国民の資金を投入する仕組みが大蔵省の真意とは。1000兆円の借金説も財務省の増税用ネタで、国のバランスシートは金融資産と30兆の徴税力がものを言い、問題ないと。ヤレヤレ。 読了日:11月11日 著者:高橋洋一  歴史が遺してくれた日本人の誇りの感想 歴史が遺してくれた日本人の誇りの感想歴史を知るための構えがわかる。実地調査をしたかのように騙る学者に要注意と。文化人類学、菊と刀はその典型と。新聞も一つの商売で昔から偏向。記事に無責任。歴史書は、創作文学で中立的歴史などない。勝者の讃歌、権力者の自己主張の都合よい内容と理解してから読み、事実を推論できるようになることが歴史通と。納得至極。吟味してから、真実、本質を考えねば騙されるらしい。聖徳太子も今や風前の存在、鎌倉幕府の成立期も変更され、足利尊氏の雄姿も別人と。歴史は、変わり、学び直され続けるもの。新聞に騙されるのは自己責任という事か。 読了日:11月6日 著者:谷沢永一  破船 (新潮文庫)の感想 破船 (新潮文庫)の感想研ぎ澄まされた話であった。著者の真髄がいかんなく発揮されていると思う。羆嵐の恐ろしさは、自然の外的脅威と、対する人間集団の性なさから醸し出されていたと思うが、破船は日本人の自然風土と、そこに生きる精神風土が織りなす恐ろしさだった。凄みのある小説の極致で著者ならではの力作だ。力強く深遠で潔い作風に息をのむ。またもや深呼吸が必要な読後だった。 読了日:10月31日 著者:吉村昭  2017長谷川慶太郎の大局を読むの感想 2017長谷川慶太郎の大局を読むの感想毎度、新聞では知りえない真相を知る。銀行の2100億ぼろ儲けはマイナス金利で失せたのではなく、預けてた分は金利温存で年2000億丸儲け。全くの無駄金。銀行の住宅ローン貸付の3割は返済遅延でマスコミは広告欲しさに事実を暴かぬと。銀行員25万人は多すぎで再編してリストラせよと。トランプが大統領になると安全保障改革が進み、露中も経済破綻するのでNATO、国連軍中心の平和な時代になると。デフレ基調は続き、量より質が勝負となり、唯一、長期資金を充分に持ち不良債権処理を済ましてる高品質技術国の日本はいよいよ強国にと。 読了日:10月28日 著者:長谷川慶太郎  一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリートの感想 一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリートの感想平和の祭典の象徴のスポーツとは異種で、勝負師、博打肌の世界一に挑んだ競技者の独白だった。崇高な精神性の評論など吹き飛ぶ、鍛錬と才能と競争心の発露が運動選手の本能なのか。理念、意義などで耐えて納得できるような世界ではなく、執念と、細心さ、大胆さを組み立てるのが世界レベルの競技者のようだ。窺い知れない極限の世界だったが、記者、陸連の現実離れした自己都合の世界はやはりそうかと想像できた。 読了日:10月23日 著者:上原善広  この日のために (下) 池田勇人・東京五輪への軌跡の感想 この日のために (下) 池田勇人・東京五輪への軌跡の感想再興、信頼回復、発展による信用獲得を目指す賢く反骨の指導者に恵まれた時代があったことに嬉しくなる。そして東京でオリンピックが開催されることの意義がとても深いものであったことを思い出せる。西欧による収奪からの独立、共産勢力による侵略を阻止、イデオロギー・民族対立、戦争の克服、こうした機運を希求する祭典であったようだ。はたして次回は「意義」をこめられるか。ショーアップに堕してしまうのか。スポーツの真剣勝負が全てを吹き飛ばして理念を体現するとよい。前回も政治屋と新聞屋が指導者を貶めて利益を謀っていたとは無残。 読了日:10月16日 著者:幸田真音  この日のために (上) 池田勇人・東京五輪への軌跡の感想 この日のために (上) 池田勇人・東京五輪への軌跡の感想豪放磊落で気持ちの良い読み物。人を思い、国を思う姿をきれいになぞり、復興、飛躍を目指す事績がとてもまぶしい。西欧文明のおぞましさ、狡猾さ、残忍さはみじんもなく、オリンピックを夢見るとはそうであったのかも知れない。市川崑の五輪記録映画でみる東京は、簡素で、小奇麗で、気高く、人々は、楽しげで、競技者は果敢に自らを鼓舞し、現代の様な攻撃的な仕草は見られない。ふるまいがとても違う。人々が集い、きそいあって、分かり合う大会であったのだろう。 読了日:10月13日 著者:幸田真音  総理の感想 総理の感想自らに都合よく事実を切り張りしながら、商売・功名欲を知的化粧顔でごまかす新聞・報道にげんなりすることがある。後日、暴露本をよんで、マスコミは事実を報道しない、自分の理屈や商売に不都合なことは捨ててしまう勢力と知ることがある。著者は長くTBSの政治記者をして退職したらしい。この本を読むと、耐えられぬもの、なせぬ事があったのではと思えてくる。 この本は、政治の実相を報道できない「ジャーナリズム」の堕落を指弾したいようだ。「プロパガンダや提灯記事に堕していないか」と。 読了日:10月10日 著者:山口敬之  遠い幻影 (文春文庫)の感想 遠い幻影 (文春文庫)の感想生と死の交錯に抗っても抗いきれない運命。受け入れるまでに費やされる年月。忘れ得ぬ月日も幻影のように変化し、ほのかな思いが宿り始める。老境に入り、全てをそそぎきったかのような心境に近づき、生き続けてきた人々は穏やかな表情をたたえるようになる。それもやがて消え去る幻影のひとつであるのだが。生きることの息づまるような迫真も、翻弄されるはかない運命も、月日を経て訪れる老境の安寧も、幻影のようにここちよいものが残る。死からも心に沁みわたる落ち着いた生が満ちてくる。 読了日:10月6日 著者:吉村昭  中東・エネルギー・地政学の感想 中東・エネルギー・地政学の感想著者と日本の半生記。日本に検証報道が欠けてるそうで、新聞、メディアではよくわからない事が、本書ではよくわかる。イスラムの動機、その道理、アメリカの動機、その野心、欧州の大罪、その狡猾がとてもよくわかる。腑に落ちた。日本の立場は独特で他国にない稀有な位置をとれると。宗教争いに安易に与せず、巻き込まれず、日本の和解の文明を賢く覚悟して示せと。夢見る乙女のシュプレヒコールなど誰にも相手にされぬと。技術を磨き、あらゆる方向を見据え、意見対立しても親交しつづけられる度胸と知性を磨けと。正しい指針に読後感はすっきり。 読了日:10月4日 著者:寺島実郎  いよいよ歴史戦のカラクリを発信する日本人の感想 いよいよ歴史戦のカラクリを発信する日本人の感想新聞、テレビ、知識人、文化人にたいする疑念、不信は、やはり正しいと思える内容。アメリカ人にこうまで書かれるとは。メディアのいびつさ、偏向・傲慢・似非報道を恥じぬ記者の跋扈、文明の商業化、知的怠惰な国民生活など、指摘は核心。バカ騒ぎのテレビは見るにたえず、傲慢な都合報道の朝日・毎日、闘わぬ知識人・文化人の偽善性・体たらく・事大性根、映画人の商業主義・映画文化の放棄、瀬島龍三・源田実等のエリートの背信、野坂参三の日本破壊工作など。嘆息しきり。 読了日:9月30日 著者:ケント・ギルバート  壊れた地球儀の直し方 (扶桑社新書)の感想 壊れた地球儀の直し方 (扶桑社新書)の感想著者の半生記。自覚、報道人としての責任感、日本への貢献の覚悟が披露され、積み重ねられた取材と培ってきたマクロとミクロからの思索、証跡の数々は興味が尽きない。事実と現象を思索して、真実と本質を明らかにしてくれているようだ。このままでいた場合の未来に寒くなる。アメリカの本質、アメリカの最大の既得権益が戦争、世界は暴力と金で動き、米、欧、中の野心も体制も壊れ果てつつあると。日本が放置してきたことをせねばならぬ切迫に納得できる。新聞、テレビの錯誤・事大はつくづくどうしようもないようだ。 読了日:9月28日 著者:青山繁晴  国のために死ねるか 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動 (文春新書)の感想 国のために死ねるか 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動 (文春新書)の感想平和に安穏に過ごす者には窺い知れないが、生死が切迫した状況に対峙する自衛隊員の心情を読めた。題意は、死ぬ覚悟をするのに値する国なのかとの疑問符だ。自分の身を守るために自分の掟を捨て他人の掟にへつらうのか。満腹でもなおも貪欲にはしたなく喰らうのか。自然の摂理を重んじてすべてと共存する理念はどうしたのか。崇高な理想を目指すなら、覚悟して守る者はおるぞ、それに値する国になってほしいとの警鐘だった。 読了日:9月22日 著者:伊藤祐靖  夜明けの雷鳴 医師 高松凌雲 (文春文庫)の感想 夜明けの雷鳴 医師 高松凌雲 (文春文庫)の感想白い航跡、暁の旅人と、時代と心意気が重なる爽快な偉人伝だ。パリ留学、箱館戦争、従軍医での事績は、武揚伝を思い出す。慈善医療、貧民医療の普及では、榎本武揚の明治への献身が読めた気がした。武揚伝ではあまりふれられなかった敗戦後の旧幕臣たちの姿が知れた。解説によると、吉村は裏付けを得られぬ事は書かないあまりに禁欲的な創作姿勢と。吉村自身は、史実そのものにドラマがあると。納得。 読了日:9月9日 著者:吉村昭  「イスラム国」の内部へ:悪夢の10日間の感想 「イスラム国」の内部へ:悪夢の10日間の感想著者に一理。西側諸国の興隆が利他主義に基づいたことは皆無と。サディスティックな残酷さは今日も何一つ変わらずと。問題なのは、権力、金、名声で、その為には恥も外聞もなく宗教の威信も悪用し、その威信も同胞の生活もなげうつと。いかなるテロも許せないが、イラク戦争も国家による最大のテロ。「聖戦」を考え出したのは、もともと十字軍のキリスト教徒。兄弟宗教のムスリムとユダヤ人を虐殺、アフリカ、アジアの異民族を虐殺、20世紀には大戦で7千万人を死亡させ、人種迫害・虐殺も。キリスト教的政治家は異教を尊敬したことなかろうと。 読了日:9月2日 著者:ユルゲン・トーデンヘーファー  羆(ひぐま) (新潮文庫)の感想 羆(ひぐま) (新潮文庫)の感想何れも非情な営みを描いた5つの短編。選び抜いた突くような簡潔な文章はいつもながら小気味よい。死者が家族を染めていく人間の宿命、重ねられていく同じ運命が暴露される。夢中になって、突き詰め、追い立て、偏執に陥り、本性と欲望をむきだしていく姿が描き出される。打算が摂理であるような物語が静かに語られる。怒りも悲しみも、青光りして、沈鬱なまま人々に蓄えられ、代々引き継がれていくようだった。発表された45年前は動物を勝負に使う時代で、その動物の性能に固執する人間像は、今では愛玩に消えうせてしまいそうだが、尚更、鮮烈。 読了日:9月2日 著者:吉村昭  世界史としての日本史 (小学館新書)の感想 世界史としての日本史 (小学館新書)の感想題名に得心。メディアは重罪で今も進行中と。溢れる自画自賛は、自虐史観のさかさまの自尊史観で、同じレベルのあやしさと。大東亜戦争敗戦、経済成長敗戦の劣等感を払拭する防衛反応と。敗戦時の参謀・外交官は、実態は無教養で愚かと。百戦錬磨、複雑怪奇、権謀術の世界で、無教養は致命的と。日本の教育は先進国で劣位、大学も遊び場、政治も勤労も愚かなスタイルと。勉強しないとやばいと。我田引水の好きなことだけ拾い読んでいては、人も国も力は身につかぬと。歴史は新事実がでてくるから学び続けよと。日本の知的退廃がよくわかった。 読了日:8月30日 著者:半藤一利,出口治明  無私の日本人 (文春文庫)の感想 無私の日本人 (文春文庫)の感想心洗われる三篇だった。あとがきで著者は、「本当にこわいのは、日本人がもっているこのきちんとした確信が失われることである。」と。とても思い当たる日々が現実のような気が残念ながらしてくる。未来をどう過ごす民族になっていくのか、今、なしている価値選択を吟味せねばと思い知らされた。渦中の世代は何を感じるか、なじまぬありえぬ思考として視野の外に捨てるのか、拝金自己実現を目標にするのか、似た規範性を社会システムに求めえると思うのか、どうなんだろう。誠実な史実書は未来を考える鏡になると思う。 読了日:8月28日 著者:磯田道史  新装版 間宮林蔵 (講談社文庫)の感想 新装版 間宮林蔵 (講談社文庫)の感想実に面白い。技術探求、冒険、外交、国防、隠密、勧善懲悪などが満載の人物伝だ。幕府逸材の高官が、筋と温情を懐に、冷静で怯まぬ武の決断をなす姿は清廉だ。その下で未知の分野に成果を求める技官の武は逞しい。扇動、情動に踊らされず、実態を実地見聞して掌握して物事を予測し、状況判断し、果断にけじめと、行く末を決めた施政は揺るがない。義のある合理性が支配する社会は、世界にひけをとらない文明とつくづく思う。 読了日:8月21日 著者:吉村昭  世界を動かす巨人たち <政治家編> (集英社新書)の感想 世界を動かす巨人たち <政治家編> (集英社新書)の感想いずれも自国の強化に邁進する指導者達で、来歴には、反骨を育んできた原体験が確認できるとのわかりやすいお話。歴史は繰り返されるとのお話で、期せずして自分が反対像の再来に化けてしまっていく様子が進行形で見えてくる。闘争的攻略的な「人種戦争」が世界で続いていると思い出す。「人間の条件1942」では為政者の冷徹を蒋介石になぞらせていたが、冷徹な自らのみへの献身は世界の為政者の共通原理らしい。 読了日:8月20日 著者:池上彰  日本人はどこから来たのか?の感想 日本人はどこから来たのか?の感想片山一道の「骨が語る日本人の歴史」では、縄文人のミトコンドリアDNA型は、シベリア、朝鮮半島、中央アジアと。渡来は5千人規模推定で縄文時代後期人口は16万人と。縄文人は骨の特徴からも世界最古の漁労の優秀な民と。本書では、アフリカ起源のホモ・サピエンスがヒマラヤの南北の両ルートで東進して、一万年後に合流し、渡海して列島にと。大陸を北上した一群は海面低下で陸続きの北海道へ進出と。対馬ルートでの進出には渡海術要と。海面低下で大陸続きの台湾から沖縄方面に渡海と。航海術の実証実験の必要性に納得。壮大で実に面白い。 読了日:8月15日 著者:海部陽介  人間の条件1942 ― 誰が中国の飢餓難民を救ったかの感想 人間の条件1942 ― 誰が中国の飢餓難民を救ったかの感想内容は、旱魃、蝗害、飢饉、逃散の中で離散した地主一族の人生だが、暴かれるのは、為政者・宗教家・支援国の腐敗と偽善。翻弄される人民の朴訥が哀しい。ワイルド・スワンを思い出すが、この本は1993年に天安門事件の悪評を打開せんと緩めた時期に間隙をぬって登場し、以後の愛国主義反日期に埋もれ、2012年にシナリオを統制されて映画化されたと。著者の責任感がなせる本。こなれた翻訳も見事。天災が人災となり、命と尊厳を蝕む国が現存する事実はやりきれない。厳しい情勢下で意図を潜ませた秀逸な本であることを訳者に教わった。 読了日:8月13日 著者:劉震雲  人種戦争――レイス・ウォー――太平洋戦争 もう一つの真実の感想 人種戦争――レイス・ウォー――太平洋戦争 もう一つの真実の感想著者はアフリカ系アメリカ人史専門のヒューストン大学教授と。訳者は1961年生まれとあるから相当の経験はありそうなのだが、機械的単語置き換え、英語構文単純置換放置文が多く、読んでもわからない修飾が複層した翻訳。内容はとても興味深く、貴重な証言資料の蒐集録のように思えるのだが、出典、引用正統性説明が皆無で、残念な編集。再編集して体裁を整えて欲しくなる。米欧豪の人種差別と収奪的侵略主義と横暴な唯一神信仰が、つい70年前まで、アジアを支配し、蹂躙し、搾取し、飽食三昧していたことが糾弾されている。 読了日:8月9日 著者:ジェラルド・ホーン  〈ひらがな〉の誕生 (中経の文庫)の感想 〈ひらがな〉の誕生 (中経の文庫)の感想日本語を作った男、上田万年では、旧仮名遣い漢文訓読みの守旧派・森鴎外の妨害にあい、言文一致の国語の近代教育は遅れ、夏目漱石の小説が言文一致の口語で実用の起点を作ったとあった。言文一致の国語は戦後となったとあった。千年前のひらがなの誕生は、日本語・ひいては大和の心の表現として登場したらしい。日本語の音を漢字借用した万葉仮名、中国古代思想を規範とする漢学からぬけだして、日本の心を表す文字として広まっていったらしい。千年隔てた、言語の変革は似た気運にあるように思えた。面白い。 読了日:7月31日 著者:山口謠司  幕臣たちは明治維新をどう生きたのかの感想 幕臣たちは明治維新をどう生きたのかの感想英雄豪傑以外の幕臣達が社会変革をどのように生きていたのか、数多くの人生模様が拾われていて、変転の実相に近づいたような気にもなるが、短い脈絡の実例が陳列気味で何が帰納できるのか、終いにはわからなくなり、混沌の社会変革に旧支配層の変転には、才覚頼みや旧人脈頼みの様々な浮沈があった、志次第の時代変革期だったとの昔ながらの理解に。体制陥落した体制人達のひとつの事例集。国民の変革の大きさを下支えした幕臣人材との、はやりの論に一石をが、編集者の意図か。 読了日:7月30日 著者:樋口雄彦  帰郷の感想 帰郷の感想何れも心に沁み込む6編だった。獅子吼の満州のさすりびとのような不思議な世界が、南方の島々、西太平洋の海底、敗戦後の占領下での銀座、新宿、復興期の後楽園で繰り広げられる。醸し出される夢うつつの中で、穢れなき人々の凄惨と、穢れた生き様の中の清廉を交互に揺らめくように際立たされていた。きらめく光とつんざく音と人々のやり取りが静かに語られ、生きたいとのつぶやきが聞こえてきた。抒情に溢れる。無言歌では、吉村昭の総員起しの鬼気を対極のように思いだした。 読了日:7月24日 著者:浅田次郎  模範郷の感想 模範郷の感想台湾、大日本帝国、中華民国、中華人民共和国、台湾語、日本語、英語と、異次元の文化が、時代を超えて折り重ねられていく不思議な旅行記だ。さまよう自身の姿が、日本家屋の鈍い色あいに溶け込んでゆくような不思議な文章だ。修飾文の重なり合いを理解するのに読み返すところがあるが、味わい深い文章だ。西洋人初の日本文学者と著者略歴があったが、八雲はどうなるのだろう。 読了日:7月22日 著者:リービ英雄  官賊と幕臣たち―列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラートの感想 官賊と幕臣たち―列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラートの感想面白い。真実のほどはよくわからないが、薩長史観による勝者の自己都合史観は半藤一利も指摘するところ。著者の言う、グラバー商会の前身と死の商人推定、薩長の武器斡旋密輸取引の取引媒介人、英の反体制派支援の野心と米仏露の牽制の薄氷均衡、幕府の先進性・国際性、長州の原理主義の残虐性、などは、司馬小説に明治維新の心地よい人間性を楽しんでいる幕末ファンには、ハードルが高い。が、言われてみればそのようにも見えてくる。歴史小説も小説であることを今更のように思い返す。吉村昭も事実に忠実だが作者として取捨する事柄はあると言う。 読了日:7月20日 著者:原田伊織  一度はこの目で見てみたい! 日本の世界遺産 (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想 一度はこの目で見てみたい! 日本の世界遺産 (PHPビジュアル実用BOOKS)の感想ユネスコの世界遺産の認定には偽善的なものを感じているが、とりあげられている歴史物はいづれも素晴らしい。写真家の手にかかれば奥行も息遣いも写し取ってきてもらえるようだ。いずこも、たたづんで時を忘れてみたい宝だ。醸される気が全く違う場の数々だ。佐渡鉱山が文化遺産にノミネートされているらしい。浅田次郎のうきよごでの佐渡の石像群を思い出す。そっと埋もれている像は掘り起こしたりしたものかどうか。 読了日:7月17日 著者:三好和義  リーダーの本義の感想 リーダーの本義の感想目頭があつい。1Fの吉田昌郎所長、伊藤忠の森本堯、オザル首相、根本博陸軍中将、エンジニアの本村洋、打撃コーチの高畠導宏、上杉謙信の本質が示される。各著作での感動を思い出す。出版社からのリーダー論の依頼に応えた本だそうだが、「この世の中でリーダーでない人など一人もいない」と禅の布教師笠倉玉溪の言葉を示し、組織に生きる人間論だ。正義、真理はかざしたとたん、不義、不浄に染まり始め、本義は、義に忠実な自分にしか宿らない、そうある人に人は靡くと言う事らしい。三菱自動車、東芝の経営者の不義の罪深さはひとしおと。 読了日:7月16日 著者:門田隆将  国会議員に読ませたい敗戦秘話の感想 国会議員に読ませたい敗戦秘話の感想数々の秘話が語られていた。朝日はじめ親中親ソ知識人の商売に戦後が闇を深めていく様には、これしかなすすべなかったものかと思う。報道が報道でなければ、見えずに狂信してしまう。その結果は、軍国主義にも共産主義にも全体主義にも社会主義にも、同質の堕落と暴力を許してしまうようだ。吉村昭の様々な戦争の記録は、歴史を正しくみよと言いたいに違いない。自らの野心を騙る筆には決して踊らず、山本幡男の「事実を通じて真実を、事象を通じて本質を掴」む信念が日本人には問われている気がする。 読了日:7月13日 著者:産経新聞取材班  戦争犯罪国はアメリカだった! ─ 英国人ジャーナリストが明かす東京裁判70年の虚妄の感想 戦争犯罪国はアメリカだった! ─ 英国人ジャーナリストが明かす東京裁判70年の虚妄の感想クエーカー教徒の著者は、白人キリスト教徒の500年の侵略・虐殺を断罪している。この野蛮の根源は、聖書の民数記のモーゼへの神の宣託、異教徒は男も女も全員虐殺し、男を知らぬ処女は分かち合えとの教えによると。非戦闘員虐殺の戦争犯罪を大統領をはじめに国家が行い、違法と衆目一致しても、正義と言い切る根底には、この教義があると。500年の白人支配を打ち破ったのが日本で、大東亜戦争で東アジアは救われたと。ベトナム、アフガン、イラクなどみれば、今でも腑に落ちる。負けずに正しさを世界に発信せよと。 読了日:7月11日 著者:ヘンリー・S・ストークス  日&米堅調 EU&中国消滅: 世界はこう動く国際篇の感想 日&米堅調 EU&中国消滅: 世界はこう動く国際篇の感想中国の崩壊回避に日銀も財務省も手を貸していると。日銀総裁のダボス会議での資本規制を認めるような発言は、中国から資産をドルや海外資産に逃がす動き防止の支援となり、中国が望むところと。中共は長谷川氏は2020年までもつまいと。田中氏はしぶとくもたすと。北は米中握って中国が電撃で倒す可能性もあると。北のミサイルは中国に一番脅威と。北と中国の人脈は完全に消されたと。東アジアは中国の正体に離反する傾向と。米は世界一の産油国になり、人口も増加しつづけ、今後も堅調。再び、米金融界が世界を支配するようだ。 読了日:7月9日 著者:長谷川慶太郎,田村秀男  戦後経済史は嘘ばかり (PHP新書)の感想 戦後経済史は嘘ばかり (PHP新書)の感想明快でスッキリできた。高度成長できたのは360円レート、石油ショックはインフレの非要因、バブルを鎮めたのは日銀ではなく違法取り締まりの成果、低成長にしたのは日銀の利上げ、日銀の目標独立性を高めた責任は大蔵省の小賢しさ、小泉政権で経済が持ち直しそうになったのも元に戻したのも日銀。著者も後知恵でわかったと言うが、皆、勉強不足と。米英は学び手をうつが、日銀は自己固執と。つくづく日本の大手メディアは信用できないことを再認識。城山三郎の描いた通産省も実は役立たず、成長戦略など国がやっても進まず、民間のみができると。 読了日:7月7日 著者:髙橋洋一  日本兵を殺した父: ピュリツァー賞作家が見た沖縄戦と元兵士たちの感想 日本兵を殺した父: ピュリツァー賞作家が見た沖縄戦と元兵士たちの感想2013年翻訳本。グアム、沖縄戦の12人の米兵証言録。吉村昭の殉国、同ノートの対極の証言録だ。地獄絵に言葉はでない。吉村の珊瑚礁も同構図のサイパンの惨劇だ。著者は、ニミッツを断罪。マッカーサー指揮なら飛び石進軍のごとく、包囲して捨ておき、ここまでの惨劇にはならなかったのではと。吉村と同様に鉄血勤皇隊の生存者の証言を録している。民間人を攻撃目標にするアメリカの戦術は、佐藤優と山内昌之によれば、リンカーンからで、厭戦醸成に市民・婦女子・老人を攻撃したと。著者の南京の被害者数引用は安易。 読了日:7月6日 著者:デールマハリッジ  崩壊 朝日新聞の感想 崩壊 朝日新聞の感想朝日の記者の著者の執筆動機は、「一言の詫びもなく」「威張り返った、そして物事をごまかす態度に愕然とした」からと。虚報、変節を営々と繰り返してきたと。エリート大卒が共産主義の階級闘争による歴史発展ドグマを盲信し、親ソ、親中が社長・役員になり、主義・空論にふけり、事実を疎かにして視野狭窄と。新聞社を隠れ蓑にした事実上の左翼結社と。戦前の苛烈な戦争鼓舞記事は、日本を米英との戦争に仕向け、ソビエトや中国の共産党への攻撃を回避し、戦争で日本を壊滅させて共産化するスターリンと同じ意図と。許されぬ。もう買わず、読まず。 読了日:7月3日 著者:長谷川熙  広島はすごい (新潮新書)の感想 広島はすごい (新潮新書)の感想「北陸資本主義」、「福井モデル」で地方の創意と地力に目を見張る思いがしていたが、広島も負けぬ熱情が回転してるようだ。仙台や福岡の人気には及ばないようなイメージが広島にはあるが、かなり「すごい」ようだ。熱帯夜に訪れた平和公園の火とドームの静けさが印象深いのだが、人々、企業は躍動的で少しも留まらないらしい。世界一のモノを造り出してきた人々と郷土であることがよくわかった。生まれる一級品に目を見張らされた。面白い。知らぬばかりで実は各地にすごいシリーズがあるのかも。 読了日:6月28日 著者:安西巧  マイナス金利の標的: 世界はこう動く国内篇の感想 マイナス金利の標的: 世界はこう動く国内篇の感想マイナス金利の意味がよくわかった。新聞社が信用できない事を再度確認。日経もアテにならないと元日経の田村秀男談。マイナス金利でも円高になっているのが、崩壊目前に資産逃避する中国富裕層、国営企業幹部の日本国債買いによるものとは・・・。二人とも安倍総理に高い評価。普天間の仕切り直しの裏話にまたあの島がとりざたされていた。上手くいけばよいのだが。 読了日:6月26日 著者:長谷川慶太郎,田村秀男  今世紀は日本が世界を牽引するの感想 今世紀は日本が世界を牽引するの感想2016年1月の本だ。春窮絶糧の歴史があるそうだ。反乱は春に起きるそうだ。食いつぶして越冬し、種を失い、反乱に追い込まれると言う図式だそうだ。中国が破綻前夜で、経済依存の韓国も逃れられず、北が破綻した時の備えはたりず、一方、中国は越流入防備を固めてあるそうだ。反日の愚を反転させた理由はこの行き詰まりにあると。重電、インフラ、技術特許、ロボット、医療産業に日本は秀で、易々とは真似できぬ。中韓の破綻には何もしてはならぬと。戦前の轍は踏むなと。さて、今年、どうなるか。 読了日:6月25日 著者:長谷川慶太郎  日本神話のふるさと 写真紀行の感想 日本神話のふるさと 写真紀行の感想古事記(ふることふみ)にそって列島の誕生から国の平定まで、神々の物語と清々しい神社、山、河、海、里の写真の数々。鳥居をくぐると古代につながるような風景のかずかず。古代を今にみせられるようでとても面白い。なんと瑞々しい国土なのだろう。神話が国土の美しさを深くしているんだ。ひとつひとつ詣でたいものだ。 読了日:6月22日 著者:清永安雄  大村智 - 2億人を病魔から守った化学者の感想 大村智 - 2億人を病魔から守った化学者の感想なんと真摯で情熱的な科学者で、人々への実益、人材の育成、美術の癒しの場、地域医療などの貢献を、探求、実現、経営したとは、驚くばかり。2012年の本でノーベル賞受賞前だが、同賞の意味がわかる科学者だ。「研究を経営」する、「経営とはもうひとつ人間形成の意味も」と。邪心なく産学共同を国を超えて調整し、経営する科学者が日本に居る。そして、人を育てている。一世紀を隔てて、北里柴三郎の偉業も受け継ぎ、事績を重ねている。あまりの人間の可能性に明日が晴れる思いだ。 読了日:6月18日 著者:馬場錬成  ロケット・ササキ:ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正の感想 ロケット・ササキ:ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正の感想電話器、レーダー、電子レンジ、MOS、アポロ功労賞、電卓、MPU、江崎玲於奈、孫正義、西和彦、ジョブスと、実用化の業績、人材育成、その「共創」の生涯には目を見張る。李登輝とは同窓で親交が続いたと。海外との技術者人脈、人望は桁違いだ。これほどの国際人がシャープを牽引していたのか。身売りは、進取の技術者が退き、牙城に固執し、新たな事業に挑まなくなった帰結だそうだ。それにしても、戦時中、レーダー技術をドイツから二人乗りのUボートで持ち帰ったと。吉村昭の深海の使者にもなかったような話だ。 読了日:6月16日 著者:大西康之  やっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人の感想 やっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人の感想司馬遼太郎のひき殺していくとの上官の発言に志が離反する話は、実は怪しいとの説明がある。丸谷元人の談話や、司馬と同じ立場の元戦車中隊長と秦郁彦との対談で怪しさが明かされた。司馬と同じ隊にいた後に学者となった人が、あんな発言は聞いていないと司馬に問うとニヤリと笑い、学者ですなあと応えたと。あの菅を江田三郎が登用したのにも噛んでいたと。志位委員長の父は、元少尉で抑留中にソ連と工作員となり、明るみになり自首し、後年、機中で突然死と。渡辺恒雄は総理の靖国参拝を認めず、皇居も駐車場にと言ったらしい。図星の指摘ばかり。 読了日:6月11日 著者:ケント・ギルバート  オキナワ論 在沖縄海兵隊元幹部の告白 (新潮新書)の感想 オキナワ論 在沖縄海兵隊元幹部の告白 (新潮新書)の感想左翼系に食い物にされている沖縄の現実、メディアの短絡報道姿勢と堕落した記者達、中国の思うつぼにはまりつつある状況、中立などとの沖縄の歴史的地政への不見識、左翼系教員、新聞による虚説の流布は深刻と。17世紀の薩摩による侵略、朝貢外交、琉球処分、沖縄戦、軍政、返還と基地存続と、もまれつづけた歴史を煽り、食い物にする運動家が国内外から流入して巣くってると。「沖縄問題」は、経済依存、左翼の非現実論での反対商売、メディアの虚説報道、読者の誤解の蔓延が本質と。この構図を産業化して生業にしている輩の存在が問題と。 読了日:6月10日 著者:ロバート・D・エルドリッヂ  日系人を救った政治家ラルフ・カー―信念のコロラド州知事の感想 日系人を救った政治家ラルフ・カー―信念のコロラド州知事の感想アメリカの憲法に謳われた個人の尊重を守る良心がアメリカ人に本当にあるのかどうかわかるかもと、期待した本。建国の信条に忠実な偉人が戦時中の四面楚歌の状況でもめげずに力を発揮したようで感服できた。それにしても、著作としては読むのが苦痛な出来で、新聞記事、手紙、公式記録など多くが未整理で文脈も途切れがちに羅列され、編集努力に疑問も。邦訳も機械的な単語の置き換えで冗長な英語の特徴をそのままのところが多数。時々、訳のトーン、巧拙が変化。はて。 読了日:6月9日 著者:アダムシュレイガー  天下城〈下〉 (新潮文庫)の感想 天下城〈下〉 (新潮文庫)の感想土木、建築、都市計画の能力は軍事力と一体で発揮されるととても大きな経済圏を作り出す。その中心が城で、城塞都市となる。実に面白い。技術力の躍動が進歩を実現していく。技術者の業績にも正負があるが、正の姿だ。吉村昭の記録文学の魅力とも似ている。事実がどこまでなのか判らぬが、地震で崩れた熊本城の石垣は後世に積んだ部位と聞くと、この話が迫真に思えてくる。日本人の核心のようで実に良い本だ。 読了日:6月9日 著者:佐々木譲  マッカーサーと日本占領の感想 マッカーサーと日本占領の感想20年以上前に発表された内容らしいが、マッカーサーの人となりが興味深い。傲岸で極めて明晰で理想家で、執念深く、自己顕示の強いエリート軍人。昭和天皇との11回の会見の解説は、戦後の日本の構築に果たした昭和天皇の力を知る内容で面白い。米側資料の発掘を著者は期待しているが、外務省にはあるのではと。バターン死の行進の責を負わされた本間雅晴中将の死刑は、マッカーサーによる偽装された復讐であると。さもありなん。戦後70年が奇跡とわかる。 読了日:6月3日 著者:半藤一利  新訳 武士道 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫)の感想 新訳 武士道 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫)の感想広い学識と愛国心と札幌農学校仕込のキリスト教信仰をもとに、武士道がなんたるか、日本人の道徳がなんたるかを見事に説いていた。1899年にアメリカで書いて出版され、日本語版は10年近く後だ。見事な日本人論で、将来の武士道を危ぶむ下りは現代の日本人の変化にも通ずるよう。欧米キリスト教社会の自己中心主義的な偏狭、一方的な独善性をジョエットなる人の引用で看破していた。キリスト教徒が世界の紛争の火種を撒いたことを感ずる。一世紀前にルーズベルトに激賞され、欧米に日本を正しく理解させたとても大きな功績。盛岡生れだそうだ。 読了日:6月2日 著者:新渡戸稲造  天下城〈上〉 (新潮文庫)の感想 天下城〈上〉 (新潮文庫)の感想獅子の城塞の戸波次郎左の父の物語。堺の切支丹豪商日比屋了珪も登場。環濠都市堺の造営、多聞山城石積みと脈々と繋がっていく事績が戦国の奔流の中で展開していく。築城能力に優れ、信長が命をとらずに抱えたものの、裏切って、信貴山城で自爆したと言う松永久秀も登場し、革新的多聞山城の建設が始まる。石積みの戦国が戦国の技術革新として重大な役回りを発揮。面白い。 読了日:5月29日 著者:佐々木譲  ナチスの楽園: アメリカではなぜ元SS将校が大手を振って歩いているのかの感想 ナチスの楽園: アメリカではなぜ元SS将校が大手を振って歩いているのかの感想ティモシー・スナイダーのブラッドランドでドイツ人とロシア人の狂気の沙汰に言葉を失ったが、その後のスターリンとの争いにダレスやフーバーやパットンがナチスを反共スパイや兵器開発に登用し、渡米を受け入れ、優遇していたとは、全く怖ろしく功利的で国益至上の陰湿陰険な国家だ。半世紀たってもどんなに高齢であっても裁く意味がわかった。それにしても米の20世紀は全く我が物とするような世紀だ。それにひきかえ、極東はつくづくカエルの楽園なわけだ。 読了日:5月25日 著者:エリックリヒトブラウ  星への旅 (新潮文庫)の感想 星への旅 (新潮文庫)の感想人間の根底にある生物として存在と、人間の経済的存在が、破綻した時、人間の実像を思い知らされると言う物語。家庭、親子の情愛はとりあげられず、生命の共同体としての住処を持つに過ぎないと描いている気がする。戦争も経済成長も貧困も人を生死に向き合わせることなのだと言う事を忘れさせない本。半世紀前の本だが、今のような読みごたえ。また、向き合えと叱咤された気になった。 読了日:5月24日 著者:吉村昭  明治十年 丁丑公論・瘠我慢の説 (講談社学術文庫)の感想 明治十年 丁丑公論・瘠我慢の説 (講談社学術文庫)の感想勝海舟と榎本武揚に対して、旧幕臣として処世を問うのが「痩せ我慢の説」明治34年らしい。佐々木讓の武揚伝では勝と榎本は対象的な人物像だ。諭吉は日露戦争の前夜に三河武士の末裔としての沽券を糺す。先進国の文物と格闘した侍が、新しい論理と科学をもとに夷狄と戦うまでになった時、忘れてはならぬもの、身を処せねばならぬ処を、偉人を借りて世に問うたのか。勝の明治はわからないが、榎本の事績は日本の礎で余人にはなしえないと思うが、諭吉は、共に新政府で富貴を求め得たことは本分にもとる、痩せ我慢せよと言う。 読了日:5月21日 著者:福沢諭吉  失敗史の比較分析に学ぶ 21世紀の経済学の感想 失敗史の比較分析に学ぶ 21世紀の経済学の感想目から鱗の話ばかりだった。数学的洞察の論理を理解しずらい知識不足の読み手に随分配慮してもらっている内容で良くよめた。論理の真偽のほどがわからない部分もあるが、納得感は満載だった。リフレの経済学者が理系からみると未熟な数理統計にあり、実態経済の複雑な要素を科学しきれていないとは驚きだ。クルーグマンも最後はアメリカ経済防衛の立ち位置にいるのを忘れるなと。軍国主義が資産収奪であった事もよくわかった。著者の国債危機観を伊藤隆敏の日本財政最後の選択と比べてみたい。 読了日:5月19日 著者:逢沢明  完全図解 海から見た世界経済の感想 完全図解 海から見た世界経済の感想著者の「国境の人びと: 再考・島国日本の肖像」では日本が宝を失いつつあることを知り滅入った。本書で海をめぐる問題の、広さ、深さ、潜む大きさを基礎学習。資源の豊かさ、競争場裏を見ると、高度技術分野でもあることを痛感。海洋分野は総合科学分野らしい。すぐれた科学者に歴史と今とそして、未来を研究・開発してもらい、日本の海の指針を見たいものだ。「島国根性」とは、今の逆の意味で、挑戦者、海の王者の精神であったとは。 読了日:5月14日 著者:山田吉彦  トヨタの強さの秘密 日本人の知らない日本最大のグローバル企業 (講談社現代新書)の感想 トヨタの強さの秘密 日本人の知らない日本最大のグローバル企業 (講談社現代新書)の感想メーカーは、実はコンテンツ産業で情報産業、知識産業であることがよくわかった。設計情報、工程ノウハウ、従業員の頭脳が、会社の本当の資産であって、原材料、仕掛品、製品在庫は資産ではなく、管理コストのかかる負債だと。売れるものだけ売れる時に造る時代だとそうなるのは実に納得。世紀の発明の財務諸表では企業の実力が読めないはずだ。「売れないものを高品質でつくってどうすんだ。犯罪だ。」と。実に頭がスッキリ。で、官民ともそうで日本はどうするんだ。実によい本。 読了日:5月11日 著者:酒井崇男  獅子の城塞 (新潮文庫)の感想 獅子の城塞 (新潮文庫)の感想17世紀の基礎土木エンジニアの修練、研鑽、留学、修行、実績、育成がヨーロッパを舞台に成し遂げられて行く歴史活劇でとても面白い。万国共通の技術者堅気が痛快でもある。史実であるのかはよくわからないが、成し遂げられると思える話。 読了日:5月7日 著者:佐々木譲  竹中先生、これからの「世界経済」について本音を話していいですか?の感想 竹中先生、これからの「世界経済」について本音を話していいですか?の感想金融会社のセミナーでの対談録。混迷、複雑系に突入し、そこそこ生きていくことに追い詰められている社会がよくわかる。勉強するようになるから、首くくらない程度に身銭切って投資やってみたらと。竹中平蔵「メディアを信じてはいけない」「経済評論家も鵜呑みせず使い分けろ」「バカは寄り集まってもバカ」。中国半分に減速してもパイが昔の倍になってるので、まだデカく、投資価値ありと。ただ、格差大の民族分裂国家なので経済難民生じたら、日本に来るので、移民法、難民法さっさと整備しろと。日本はもはや金だけでは済ませぬ立場と。 読了日:5月4日 著者:竹中平蔵,佐藤優  天才の感想 天才の感想著者があとがきで言うとおり、あの当時、皆が洗脳されていた。占領政策、東京裁判、変節新聞社の正体を見抜けなかった事と同じ事が起きていた。まさか司法までとは。冤罪看過の事大裁判を知れば不思議はないが。愛国者を失ってしまったこと、遺した業績に大器を失ったこと、成し遂げたことに気づく。ニクソンは、1971年8月15日に平和のための挑戦としてドル防衛を発表し、日本人につけをまわし、佐藤にわざと恥をかかせたと後年明かす。執念深く周到な国だ。構図は悪徳の勝者、公徳の敗者だ。 読了日:5月3日 著者:石原慎太郎  碇星 (中公文庫)の感想 碇星 (中公文庫)の感想生死を目のあたりにした人の人生観は、生命を育まれ続けて過ごしてきた餓えたことのない人と隔絶がある。覚めて熱狂の次にあるものを本能的に予期してしまう習性のような違いだ。個人の自分の時間と、自由の共有の打算、その間にある本性の厳然たる違いの実存。このリアリティーが静かに目前の足下に横たわる。静寂な原理が人に課せられているようだ。吉村昭には向き合えといつも叱咤される。 読了日:4月30日 著者:吉村昭  VWの失敗とエコカー戦争 日本車は生き残れるか (文春新書)の感想 VWの失敗とエコカー戦争 日本車は生き残れるか (文春新書)の感想公表資料、報道、伝聞の陳列本。表題のVWは失敗ではなく、犯罪のはず。エコカー開発は競争であって、企業戦争でもなく、収奪的な進め方では実現できない技術競争分野。テスラがZEVのクレジット取引による金融利益狙いとの指摘はさもありなんと。本書で並記の三菱自のリコールとトヨタのリコールは別次元の質の差があり、前者は刑法領域。三菱自に人材・技術・戦略ありと好意的評価には驚いた。新書で珍しい表題のつけ方にひっかかり空振り。 読了日:4月29日 著者:香住駿  日本語を作った男 上田万年とその時代の感想 日本語を作った男 上田万年とその時代の感想現代の日本語が明治に生まれ損なって終戦後に開花したとは。それまで、言文乖離の不便に国民は晒され続けていたとは。民意の言文一致の仮名遣いを10年教育続けたにも拘わらず、国語国字の制定に向かおうとした時、森鴎外が陸軍軍服姿で三時間の反対演説をして旧仮名の時代に反転していたとは。文部省教育が留まるなかで、漱石作品や唱歌で言文一致が広まっていたとは。その前線の上田万年なる言語学者の愛国心は威圧人格の鴎外とは異次元だ。実に面白い。 読了日:4月29日 著者:山口謠司  望遠ニッポン見聞録の感想 望遠ニッポン見聞録の感想しなやかで健全でまじめな人生観。とても楽しい。異文化、異民族もこのように面白くとらえられれば世界平和が広がるだろう。違いを当たり前として受け止め、深刻にならず、何事も面白がる。苦労も異様な経験もあとになれば滑稽気味に受け流し、多様性を寛大に楽しむべきらしい。肝がすわっている。核は、安直な理解をしないで実態に向き合って格闘してきたことらしい。自然児で動物昆虫の類と仲良しでもあったらしい。デルス・ウザーラを尊敬していて、息子の名にしてしまうまでとは。日本は「味わい深い」そうだ。ナパージュ人にはわかるまい。 読了日:4月24日 著者:ヤマザキマリ  歴史問題をぶった切る《最終解明版》 占領支配者が謀った《国魂(くにみたま)占領》の罠 (Knock‐the‐knowing)の感想 歴史問題をぶった切る《最終解明版》 占領支配者が謀った《国魂(くにみたま)占領》の罠 (Knock‐the‐knowing)の感想朝日、山川、大学教授を一刀両断する小気味良いものだったが、落ち着いた整理本も読んでみないととも思う筆致。教科書が自虐的な歴史の派閥の権益に独占され、商売として支配されているとなると、学生が日本史には近寄りたくなくなるのは当然だ。日本史が必修でなくなり、世界史が必修の国はおかしいとの指摘はもっともだが、今の教科書では必修にするのは反対との論も迫真。歴史教育は日本にはまだないかのようだ。歴史学者は何をしているつもりだったのだろう。学問は孤高のはずなのだが。 読了日:4月19日 著者:倉山満,藤岡信勝,竹内睦泰  新版 流れる星は生きている (偕成社文庫)の感想 新版 流れる星は生きている (偕成社文庫)の感想新京から博多まで13か月の苦難の日本への帰還を、乳飲み子、6歳、3歳の子をつれた母親がひとりで成し遂げた壮絶な生還録だった。著者は新田次郎の妻で、新田次郎が小説家になるきっかけとなったそうだ。日本人の「根性の底までさらした」著述で、人間性がえぐりだされていた。こうした事態を造りだした軍閥と新聞社の戦争責任は測り知れない。 読了日:4月17日 著者:藤原てい  新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(下) (講談社文庫)の感想 新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(下) (講談社文庫)の感想国力差、技能差が大きくて、簡単には追いつけない相手に囲まれ、軍事力で威嚇され、付き合いを強要される状況とは、心細く、不安で、方針も定まらず、付和雷同するのがおちだ。ひるまず、媚びず、奢らず、機知にとみ、良識にもとづいて、巧妙に、そして正直で誠実に思考、交渉できた人物伝だ。そんな人材を非エリート層から輩出・登用した武家社会とは人間形成が隔てなく実践される文明だったのか。盲目的狂信的滅私の封建精神ではなしえない事だ。150年後、理財と経済に精神支配され、人間が狭窄、偏向した国になっていないかどうも気にかかる。 読了日:4月16日 著者:吉村昭  新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(上) (講談社文庫)の感想 新装版 落日の宴 勘定奉行川路聖謨(上) (講談社文庫)の感想侍たちが、自然科学と人文科学を手探りで学び、試し、体得し、国を近代化し、交渉の末に国際化していく様が描かれている。物理、道理、法理が実行できたのは、幕藩体制下での人間修養による基礎鍛錬によるものとよくわかる。「出島の千の秋」の西洋植民地主義との戦い、「武揚伝」の技術意欲と蝦夷開拓と海洋冒険、「日本、遥かなり」のエルトゥールルの奇跡などの感動が全部入った人物伝で、聡明で賢明で、謹厳で勇敢で実直で仁愛な日本人史。こうした歴史理解があれば、道は誤らないですむのでは。 読了日:4月10日 著者:吉村昭  豊田章男が愛したテストドライバーの感想 豊田章男が愛したテストドライバーの感想トヨタの芯がまたひとつわかる本だった。考え方、やり方、育て方、関わり方をいろいろな紹介本で見聞するとメーカー道のように思えていたが、それを体現した社員の人生と、応えた経営者の物語で、仕事に清廉で賢明で真剣な姿勢がとても崇高だった。完成させるために徹底した思考と行動に格闘する社員がいる会社の凄みに圧倒されるが、繰り広げられる人間模様は感動的だ。企業の管理的弊害を吹き飛ばす人物伝だ。 読了日:4月3日 著者:稲泉連  新・地政学 - 「第三次世界大戦」を読み解く (中公新書ラクレ)の感想 新・地政学 - 「第三次世界大戦」を読み解く (中公新書ラクレ)の感想世界史の転換期にあるそうで、戦争、核拡散、石油エネルギー争奪、ロシアの軍事成果拡大、イスラムの宗派主義での殲滅抗争化などが進展して、中東、中央アジア、ヨーロッパが内戦、大戦の危機に瀕しつつあるそうだ。日本では人物が活躍せず、世界史から脱落すると。反知性的な政治と外務省の無能ぶりはかってない惨状だそうだ。科学と人文の教養を身に着けた政治家を選び、押し立てないと日本は瓦解の末路を遂げてしまうらしい。なんとも迫真な話だ。目先に安住せず中期戦略に力と頭を奮えと。軍事や国際法を教養として学ばんのは日本だけらしい。 読了日:3月29日 著者:山内昌之,佐藤優  闇を裂く道 (文春文庫)の感想 闇を裂く道 (文春文庫)の感想大正7年1918年から昭和39年1964年までの新旧丹那トンネル工事を通じた、昭和の世相史だ。技術と自然と経済に人々が格闘する物語だが、誠実で控えめで、堂々とした官・民の対峙が端的に描かれ、日本人の熱烈と堅忍と蛮勇と正義観とが併存してなんとか解決を導き出す苦難の人間的特性がよくわかる。事故、事件、騒擾、自然破壊の数々の出現に驚く。自然と格闘する日本人は征服的で冒険的であるのだが、惨劇を乗り切る決着はいづれも日本的で救われる思いがした。この本も圧倒的だ。苦難を新幹線に結実させる歴史の重層の見せ方も見事だ。 読了日:3月23日 著者:吉村昭  サッチャーと日産英国工場――誘致交渉の歴史 1973-1986年の感想 サッチャーと日産英国工場――誘致交渉の歴史 1973-1986年の感想題は良いが、学籍者としてのなんらかの実績づくりの代物かも。索引や引用注記、前書き謝辞、あとがきの自分史披露の本としての体裁は立派な学術書の体裁。それだけで51ページ。本文は183ページ。短いので、完結明瞭論旨かと思うと、二次資料の引用も多く、読書メモのような印象も。感想文のような部分もあり、学術なのか文芸なのかよくわからなかった。他書の引用で構成された節も目立ち、取材にもとづくノンフィクションでもなかった。事実を通じた真理も事象を通じた本質も分からなかった。 読了日:3月18日 著者:鈴木均  カエルの楽園の感想 カエルの楽園の感想ストレートな寓話仕立ての風刺で、迫真、予感に溢れた物語だった。国の運命を人にゆだねる倒錯した屈折が見事に描写されていた。無言の生きる意志が扇動の思想暴力に負けていく様が痛々しい。こうした抗議本で国の平衡感覚がとりもどせることになるのかわからないが、あたっているとの読後感。高見順が言った厚顔無恥の変節メディア、それはまだなくならないとの諦めがまた思い出さされた。 読了日:3月15日 著者:百田尚樹  兵士は戦場で何を見たのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ II-7)の感想 兵士は戦場で何を見たのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ II-7)の感想ウィキリークスの暴露動画で攻撃ヘリからのジャーナリストと民間人の虐殺シーンをテレビで見て震撼したが、そのシーンは、その暴露の前年2009年にこの本で暴露されていたそうだ。許可にもとづく軍事行為で免責の手立てを準備してある。おぞましい。ベトナムの民間人大量虐殺軍事行動の正当化論理と同質の原罪を彼らは21世紀もいまだ保持しているのか。米兵の痛みが子細に書かれているが、戦場にされた民の悲劇や痛みの取材内容はなく表情描写にとどまる本。アメリカの為のアメリカメディアの本と言う事か。 読了日:3月14日 著者:デイヴィッド・フィンケル  B面昭和史 1926-1945の感想 B面昭和史 1926-1945の感想庶民の世相、風俗日記は、不景気、神道、軍国教育の素顔をみるよう。新聞の風潮、世論の扇動記事に今のメディアに似たような気質を感じてしまう。当時の新聞報道の実態がよくわかり、日本の行く末に正論ぶった評論で自己顕示する評判ねらいの今の商売紙をみるようだ。昭和8年までの読後感。 読了日:3月11日 著者:半藤一利  決定版 - 武揚伝(下)の感想 決定版 - 武揚伝(下)の感想戊辰戦争の義士達の心情が切ない。近代戦であったことが、英知に富む向学の徒でもあった武士の運命が、尚更痛ましい。政治に生きて軍の人心から見放された勝海舟と、信義と技術の実用に生きて人心をえた榎本武揚の対比は、鮮烈だ。薩長史観で毒された歴史観、司馬史観での爽快な人物史観と全く違う気持ちの良い人物伝だ。実力と人格が激動の時代の要求に応えられる偉人だ。戦争後の要職歴任は立身出世とは別次元の活躍の結果であるとの解釈には得心。史実を基礎にした小説と明言する著書は実によい。 読了日:3月8日 著者:佐々木譲  決定版 - 武揚伝(中)の感想 決定版 - 武揚伝(中)の感想口先政治家の勝が徳川家、慶喜存続に腐心する傑物としての視点がでてきて面白い。咸臨丸組から総スカンで人望を失い、薩摩と親密な関係を持ち無血開城の努力も、上野の彰義隊の戦争を招き、徳川家の存続を絶ったと。薩長軍は狼藉・乱行・私怨・独裁政権欲・君側の奸と。面白い。共和国、議会制展望、独裁政権打倒の戊辰戦争としての史観、失業幕臣対策としての新天地国家建設野望も胸がすく。現実は、「赤い人」で佐幕藩が下って開拓した村が出てきた。県令、屯田兵の薩摩支配もあった。 読了日:3月6日 著者:佐々木譲  日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てたの感想 日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てたの感想「生きて帰ってきた男」に、良く運営され何か成し遂げたかのような収容所があるなどとは信じられぬと言うような述懐があったと思う。飢餓、寒さ、同胞からの思想弾圧、同胞内の階級差別などの過酷さからの生還だったようだ。「収容所から来た遺書」には、飢餓、弾圧、過酷労働下での不屈の同胞愛があった。本書では、仕事への誇りと生命への尊厳を守り通した勤労者の姿があった。何れも高い精神性がうたわれていた。本書でも、同胞の大量の名簿を暗記して日本に帰還している。日本再起の起点に違いなく、胸に迫る。 読了日:2月28日 著者:嶌信彦  決定版 - 武揚伝(上)の感想 決定版 - 武揚伝(上)の感想蘭学への学習意欲、実用技術への渇望が自身に運命を呼び込み、見識を磨く境遇を与え、オランダ人との250年の友誼を知り、蘭仏英独の世情、最新技術・産業、近代戦を実見し、日本の近代化と存亡危機克服に仕えようと決意するまでの爽快な物語だった。技官の実学視点がよい。勝海舟が口先政治家で海軍能力欠如、咸臨丸艦長は虚勢、島津薩摩と交誼、自己顕示と散々。半藤一利は、福沢諭吉が「痩我慢の説」で勝を悪く言うのは対立していたからで、事実は違うと言うが、著者は咸臨丸で勝は役たたずで、操船ままならぬ駄々こねる輩と。面白い。 読了日:2月28日 著者:佐々木譲  新装版 赤い人 (講談社文庫)の感想 新装版 赤い人 (講談社文庫)の感想明治時代の懸命で前途に果敢に挑み、学び、努力し、薄氷の勝利を手中にする爽快さは、楽しい読書だ。その対極だ。「破獄」で昭和の庶民の素顔を読んだが、この本では明治の生活者の素顔をみたようだ。文明開化の底辺では、暴力と功利と権勢欲が支配しながら、国を近代化し、北海道の殖産基盤が作り上げられていたのがよくわかる。生死に支えられた開拓らしい。「雪の墓標」を思い出す。昭和の戦時もまた、この状況と似た人々が北海道に遺されていた。 読了日:2月27日 著者:吉村昭  ドイツリスク 「夢見る政治」が引き起こす混乱 (光文社新書)の感想 ドイツリスク 「夢見る政治」が引き起こす混乱 (光文社新書)の感想ドイツは、過去を反省し謝罪したのに日本はそれのできない劣等国で、歴史を隠蔽し、自己を正当化する罪の意識に欠ける民族とドイツメディアは報道しているそうだ。中国の反日運動に同調し、日本は歴史問題を克服しない問題国と報道されているそうだ。メルケルが来日時に朝日新聞主催の講演会を引き受けたのは政治目的と。英、米、仏とは全く違う国で自己に固執陶酔し、他国をあげつらう国と。自ら贖罪成果と振りかざす、優越主義者と。中国経済偏重国。やはりそうなのか。原発事故への態度は正体で、ユーロ不安、移民、南欧格差と混乱招く素地大。 読了日:2月26日 著者:三好範英  戦国はるかなれど(上) 堀尾吉晴の生涯の感想 戦国はるかなれど(上) 堀尾吉晴の生涯の感想信長の躍進と秀吉の大返しまでの数々の戦話と武士の逸話がめまぐるしく綴られていて、人物、城、戦史に翻弄されるような読後感。戦国逸話が洩れなく盛られているようで戦国史棚卸のような読後感。星野遊呆さんの「年表でみる戦国時代」の城郭地図が重宝した。人物伝はそれほど多くない戦史で、脇役から見た英雄伝のような印象。 読了日:2月23日 著者:中村彰彦  米中激突で中国は敗退する―南シナ海での習近平の誤算の感想 米中激突で中国は敗退する―南シナ海での習近平の誤算の感想新聞メディアの報道はなんなのかと思うばかり。珊瑚の残骸で埋め立てた滑走路など米軍には脅威でなく、米軍の自由航行の確保が米国への核攻撃原潜侵入阻止のための至上命題と。示威行動により共産党の面子が国内向けに保てればよいのが本音で、戦争したら石油も断たれ負けるとわかっていて、対抗できそうなサイバー攻撃と衛星破壊に賭けてるそうだ。国務省はその時に備えて米人を送るな、留学生上がりを採用しろと企業に人事介入してて、GMの現地の米人は一桁と。トヨタは数千人の邦人と。毎朝、北京は大丈夫かと確認するそうだ。 読了日:2月14日 著者:長谷川慶太郎,小原凡司  2020年 世界経済の勝者と敗者の感想 2020年 世界経済の勝者と敗者の感想消費増税は止めよ、同じ徹を踏むなと。また景気を折るのかと。消費増税しないと財政破綻すると言うのは財務省の嘘と。財務省はIMFなど海外にも嘘を言い、自省説を日本に還流させようとしたと。真に受ける投資家もいて危険と。日本の国債は格付け下げられても低利で安定評価。投資家はわかっている。対外純資産世界一で官民資産が厚く、南欧とは全く違う。格付け会社は商売の手段で格付けし、客観的ではなく、政治的思惑も。ユーロは独善的欧州体質で生まれ、失敗と。政治統合なしの通貨統合は疑わしいと。とてもわかり易い。 読了日:2月13日 著者:ポール・クルーグマン,浜田宏一  シャルリとは誰か? 人種差別と没落する西欧 ((文春新書))の感想 シャルリとは誰か? 人種差別と没落する西欧 ((文春新書))の感想冒涜する権利を訴える社会が自由と平等と博愛を標榜するのがどうしてもわからなかったが、実は平等も博愛も色あせて、神への信仰を失った空白感をユーロで埋めようとしたものの、信仰による慈愛、同情の義務から解放されてしまい、不平等のヨーロッパができてしまったそうだ。倒錯していてユーロの失敗の生贄にイスラム教徒をしたてたらしい。若者の痛手が手当されず、高齢者層が有する許されるべきでない特権も顧みられない社会だそうだ。シャルリは団結などしていない中産階級のフィクションらしい。仏は政治的崩壊過程と。不気味な世相だ。 読了日:2月11日 著者:エマニュエル・トッド  小倉昌男 祈りと経営: ヤマト「宅急便の父」が闘っていたものの感想 小倉昌男 祈りと経営: ヤマト「宅急便の父」が闘っていたものの感想中山素平を高杉良が描いた「勁草の人」を思いだした。興銀が志に溢れていた時代の産業振興にかけた人物伝で、晩年は若者の国際教育に捧げられた人生に感銘したが、冷めた夫婦関係の記述、別宅の生活も明かされ、作者の記述意図は何かとも思った。本書は、途中で興味本位に媚びる内容かと用心し、果たして小学館は何を賞したのかとも感じてしまったが、最後まで読むと表題、副題の意味もよくわかり、改めて人物の大きさ、崇高さに胸を打たれた。没後10年を経て、関係者の現在を見極めての立派な著作だった。 読了日:2月7日 著者:森健  定本 黒部の山賊 アルプスの怪の感想 定本 黒部の山賊 アルプスの怪の感想黒部の猟師が滅びる最後の姿と北アルプスとしての黎明期が著されていた。怪談、奇談、冒険談あり、人間性を問うような遭難にみる人間模様もある。昭和39年初出らしいが、秘境生活者への世相の影響も分かり、戦後の世の中の雰囲気も感じられる記録だった。黒四ダムがオーバーフローしたこともあるとは。吉村昭ばりに猟師が描かれていると感じた。「あからさまな人間性」「欠点だらけ」でも「心惹かれる」「山賊」達。とても面白い。 読了日:2月6日 著者:伊藤正一  沖縄の殿様 - 最後の米沢藩主・上杉茂憲の県令奮闘記 (中公新書 2320)の感想 沖縄の殿様 - 最後の米沢藩主・上杉茂憲の県令奮闘記 (中公新書 2320)の感想米沢藩最後の藩主上杉茂憲の沖縄県令の事績を通して、明治の中央政府の支配と沖縄の被支配の歴史がよくわかる。17世紀から薩摩藩に支配されるも日清両属の思想が根付き、明治政府は皇民化教育で改造しようとしたそうだ。怨念が底にあると著者は言う。皇民化教育は沖縄戦の惨劇に繋がり、アメリカ支配、日本復帰も心の底にあるものを更に硬くしたのだろう。美しい穏やかな人々の歴史が昔からこれほど厳しいとは・・・ 読了日:2月4日 著者:高橋義夫  最終戦争論 (中公文庫BIBLIO20世紀)の感想 最終戦争論 (中公文庫BIBLIO20世紀)の感想昭和15年5月講演録。「今、米は全艦隊をハワイに集結して日本を脅迫」。ドイツは一次大戦後、産業革命して機械化兵団と空軍質量差で欧州弱者に短期勝利。連合側の物心両面劣勢は必然。後30年で最終戦争になると。男子皆兵に加え老若男女全員に耐えを求める戦争となる。空中戦が中心で瞬時に都市を壊滅する兵器が運用され、世界人口は半減するやも。喧嘩好き西欧覇道文明は、弱い人々と重要施設を破壊目標にして殲滅作戦をとる。日本は備え、民族協和をめざせと。今でも大統領がまず国益を口にする国は当時とあまり変わらないのか。 読了日:1月31日 著者:石原莞爾  伊藤正一写真集 源流の記憶 「黒部の山賊」と開拓時代の感想 伊藤正一写真集 源流の記憶 「黒部の山賊」と開拓時代の感想三俣山荘、雲の平山荘、水晶小屋、伊藤新道の建設整備の記録写真、北アルプス深奥の美しさ、冷厳さ、芽吹きの記録写真集だ。槍ヶ岳の月光、朝焼け、氷雪の姿は峻厳でやっぱり孤高に見えた。上流階級の世界、「山賊」の時代、発電国策の時代、自然を愛する大衆登山の時代、変遷がよくわかる。「人はなぜ山に登るのか。背後に社会があるからだ。」と著者は言う、山岳文化はまさに社会の生き写しで汚すも隠すも育むも文明水準次第と言う事だろう。くしくも山々の自然との関係が、日本人の文明水準を明らかにしているようだ。 読了日:1月29日 著者:  五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後の感想 五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後の感想石原莞爾の試案で辻政信が骨格づくりした満州国最高学府の卒業生達の戦中戦後の記録だった。民族を超えて生きようとした青年の希望と米ソ欧のアジア侵略との格闘。共産主義、軍国主義、民族主義いずれもが残忍で、自らの知識と思考に未来を探す青年達の健全な死闘録だ。朝日新聞の記者が書いたものなので自社都合の切り取り、切り捨てに用心して読み始めたが、証言記録は胸に迫るものばかり。論証抜きの断定的歴史観形容詞が一部余分に感ずる程度の「角度」。良い本。 読了日:1月28日 著者:三浦英之  佐藤優の「地政学リスク講座2016」 日本でテロが起きる日の感想 佐藤優の「地政学リスク講座2016」 日本でテロが起きる日の感想報道では知りえない内容ばかり。イスラム過激派の仏でのテロが意味するもの、北方領土の現実的行方、ウクライナ問題は独、仏も国益で動き、露の勝利で合意、ウクライナ指導者の暗部は歴代深い、IS支配地域への人道支援の敵対的意味の大きさ、核の新たな拡散危険性、韓国のナショナリズムの行方、反知性主義の表層化等々、どれも得心。著者の本を読むと新聞は本当に取材して書いているのかわからなくなってくる。 読了日:1月26日 著者:佐藤優  獅子吼の感想 獅子吼の感想吉村昭の「動物園」を思いだした。戦時中の上野動物園での薬殺で、飼育員の悲しみが描かれていた。薬入り馬肉を食べないライオン。飢えで追い込まれて食して絶命する百獣の王だった。獅子吼の西山動物園は仙台動物園なのだろうか。Wikiだと花壇にあったらしく、たしか広瀬川の蛇行した洲だ。西の山上にある八木山動物園は戦後らしい。収録6編とも人の真心を問う心に沁みる話だった。 読了日:1月24日 著者:浅田次郎  破獄 (新潮文庫)の感想 破獄 (新潮文庫)の感想軍国主義の深まる時代から民主主義を自己流に試し始める時代までの間に繰り広げられた、最強の公権力行使である刑務所への抵抗となる脱獄の人間模様が描かれているが、時代とその時の人々の真実をみるようだった。モデルの人の実生活を守る為の仮名小説だが、日本人の経験した事象の本質が記録されていると思う。 読了日:1月24日 著者:吉村昭  山本五十六の真実―連合艦隊司令長官の苦悩の感想 山本五十六の真実―連合艦隊司令長官の苦悩の感想英雄の逸話、私信の真情を読み、伝え聞いていた英雄像が実像であると思える内容だった。「社会科学上一つの概念は筆者の嗜好によって左右することは慎まねばならないが」と著者は書いているが、著者の英雄への敬愛が出ていた。つくづく、英雄を追い詰めた戦争体験のない成績エリート軍人達の偏屈と陶酔と保身と徒党に嘆息。本の編集は、節の寄せ集めで時系列入りくり、事績の重複、文脈飛躍に気が散った。 読了日:1月22日 著者:工藤美知尋  忘れられた島々 「南洋群島」の現代史 (平凡社新書)の感想 忘れられた島々 「南洋群島」の現代史 (平凡社新書)の感想沖縄戦の惨劇に先立ち、沖縄からの移住者の惨劇がサイパン、テニアンなどで起きていたことも忘れてはならないと。軍の考えた本土の捨て石に多くの人々の命が失われたそうだ。兵士、軍属そして家庭人、その子供達。南洋群島の現代史も17世紀からの西欧の差別、収奪、暴力の変遷と本質は変わらないと思えてしまう。南洋群島を舞台に20世紀の文明の正体を暴くかのようだ。もっと考えよと言われたようだ。良い本。 読了日:1月19日 著者:井上亮  蚤と爆弾 (文春文庫)の感想 蚤と爆弾 (文春文庫)の感想あとがきで保坂正康が主文脈で名を与えられたのは一人のみで、他は無名の役職表現をとる匿名形式のノンフィクションと。冷静な筆致で興奮した告発はないと。まさにそのとおりの吉村昭作品だった。描写事実と人間像に、日米ソとも、非人間性でみれば同じ穴に巣食う無限の暴力性を備えた同罪の国家であることがわかる。軍事と科学分野で人間はとんでもないことをしでかす存在と分る。非難告発表現なしにこれでいいのかと問われた。 読了日:1月14日 著者:吉村昭  賊軍の昭和史の感想 賊軍の昭和史の感想薩長史観、薩長の軍事行動での成功体験が、その後の軍事学と軍事思想の健全な進歩を歪め、成績至上の暗記軍人が戦争知らずのまま、参謀となり、天皇の大権を越権して、敗戦時のことを思考せず、人々を死に追いやったと。偽の錦の御旗で官軍を装い、政敵を虐殺した戊辰戦争と酷似。主犯の参謀達は天皇責任問わずにより責任追求から逃れたと。終戦に持ち込み日本人の命を繋いだのは、賊軍派の要人の力だそうだ。陸海エリート参謀の罪ははかりしれないと。 読了日:1月11日 著者:半藤一利,保阪正康  2020年世界はこうなるの感想 2020年世界はこうなるの感想著者の情報と予測には、今回も、なるほどと思わずつぶやく事しきりだった。天津爆発の原因と影響、中韓が日との首脳会議へ急転回した理由、米中首脳会議の直前に安保法制が成立した狙い、米軍は前線での共同作戦を拒否する国がある、VWの体質とその未来、メルケルがプーチンを支持する理由、人民解放軍との確執とその国の未来、北朝鮮の干ばつ、拉致の全貌、その時の中国からの影響・・・日本の未来を信じてよさそうな気分に 読了日:1月9日 著者:長谷川慶太郎,田原総一朗  出島の千の秋 下の感想 出島の千の秋 下の感想「帳簿の世界史」にあったオランダの世界制覇と衰退の中で会計が果たした役割を思いだした。この本でも極東での交易と商館経営の歴史が帳簿で紡がれていて物語の基底にあった。負債は資産だとのセリフもあった。植民地経営、海上交易、商船、海軍と、日本の封建社会、侍文化の関わりがとても面白い。米、英、蘭、独の違いも鮮やか。現代の風刺にも思えてきた。よくできた時代劇。 読了日:1月8日 著者:デイヴィッドミッチェル  出島の千の秋 上の感想 出島の千の秋 上の感想著者は、英国生まれで広島で日本語教師を8年していたらしい。原文は英語だそうだが、自然な日本語に翻訳されていて見事な江戸時代劇になっている。驚きだ。長崎に無数の煙突、九州山中の積雪、寺に毛布など時代風俗考証で少し気になったが、寛政の日本と植民地支配の世界情勢の凝縮が面白い。史上初の株式会社で世界の価格を支配していたオランダ東インド会社での出世争い、私利私欲ぶりは企業小説。鎖国行政と開化探求は歴史小説。その噛み合いは面白い。 読了日:1月5日 著者:デイヴィッドミッチェル  ヨーロッパから民主主義が消える (PHP新書)の感想 ヨーロッパから民主主義が消える (PHP新書)の感想「事実を通じて真実を、事象を通じて本質を」知ることが大切と「収容所から来た遺書」の主人公の言葉があった。新聞は自社角度の保身に執着で報道すべき事実がされてないと思うが、この著者の話は真実に近づけた気になれる。ヨーロッパ民主主義は多分にご都合主義でキリスト教徒の名で犯してきた罪と偽善に気づかない限りイスラム問題は解決しないと。イスラム過激派はヨーロッパが育てたと言ったら言い過ぎかと。 読了日:1月2日 著者:川口マーン惠美 読書メーター |